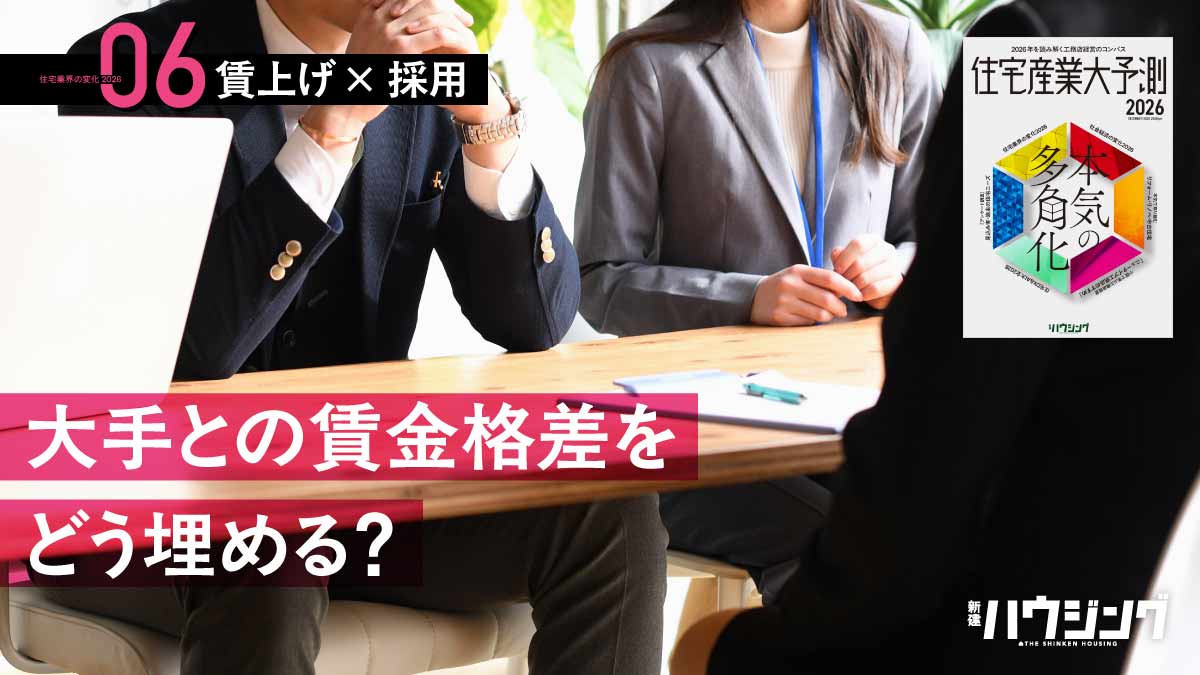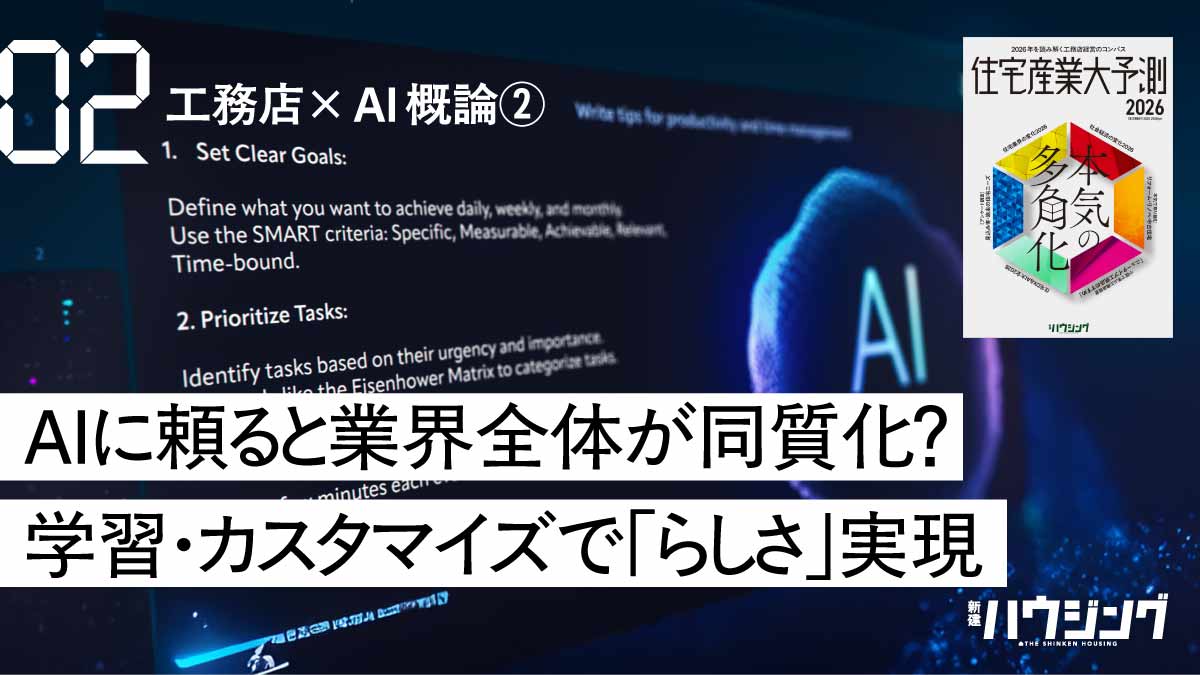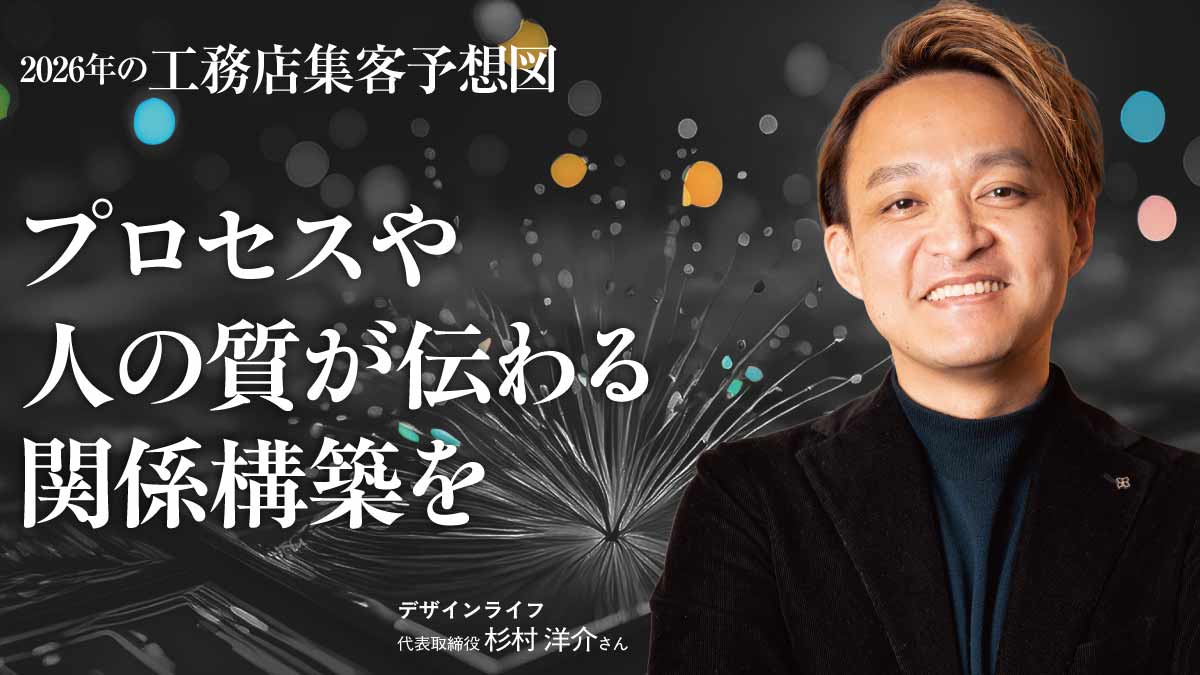|
三澤 文子 建築家・エムズ建築設計事務所 |
エムズ建築設計事務所代表取締役、住宅医協会代表理事、岐阜県立森林文化アカデミー客員名誉教授。静岡県生まれ。1979年奈良女子大学理学部物理学科卒業、現代計画研究所を経て1985年、夫・三澤康彦とMs建築設計事務所設立。主な作品に「ケナル山荘」「白水湖畔ロッジ」「禅定庵」「北沢建築工場」「宍粟わかば」など |
改修の柱は耐震・断熱・耐久
1995年、阪神大震災が起きたとき、私は大阪にいたがかなりの揺れを感じた。その後、被災地での調査活動にも従事し、設計活動が180度変わるきっかけになった。昨年1月に発生した能登半島地震でも住宅の被害が大きかった。耐震性に問題のある住宅はまだたくさん残っている。
断熱・省エネ性不足の住宅も多い。エアコンが効かず寒いから、と開放型の石油ストーブでエネルギーを浪費する。脱衣室や浴室はヒートショックを起こしかねないほど寒々しい。耐震と断熱・省エネは改修の2本柱。耐震には劣化(耐久性)も必ずセットになるので、実際は耐震、断熱・省エネ、耐久性の3つがマストであると言える。
私たちは20年ほど前から住宅医として “今ある建物の病気を治して、よい建物を残していく”ための活動を展開してきた。設計者としても、先ほど挙げた耐震性、温熱性、省エネルギー性、耐久性(劣化対策)に、バリアフリー性、火災時の安全性を加えた6つの性能が、現状より改善・向上することを目指して改修の計画を立てている。
調査こそが設計の基礎
設計を始める前には必ず調査を行う。住宅医では、まず事前調査として建て主のヒアリング(「住まいの問診」)、図面や確認申請図書・検査済証の有無、改修の履歴などを通じて現況を把握する。それから詳細な調査を行い、各性能を診断する。例えば耐震は、基礎が有筋か無筋か、耐力壁の要素(筋かいや金物、火打ちの有無)といった、構造的な特徴がわかって初めて耐震診断ができる。
一方、柱の直下率は、診断ソフトには反映できないので、調査した設計者が分析すべし。古いわりにいいプランだなと思っても・・・
続きは「あたらしい工務店の教科書2025」P.28〜でお読みいただけます。
\あたらしい工務店の教科書2025・まとめ買いはこちら/
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。

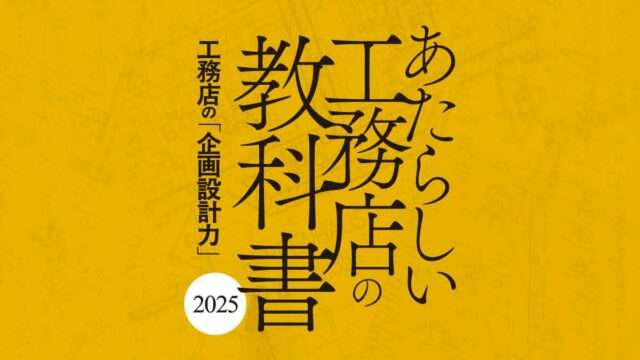

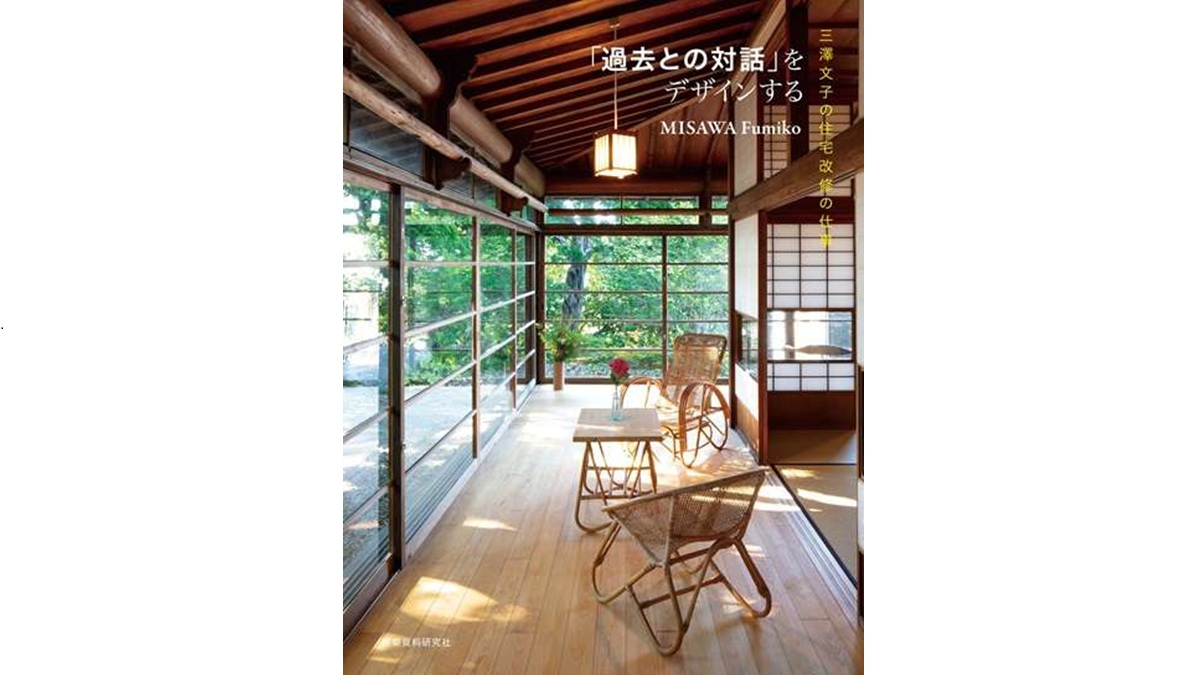

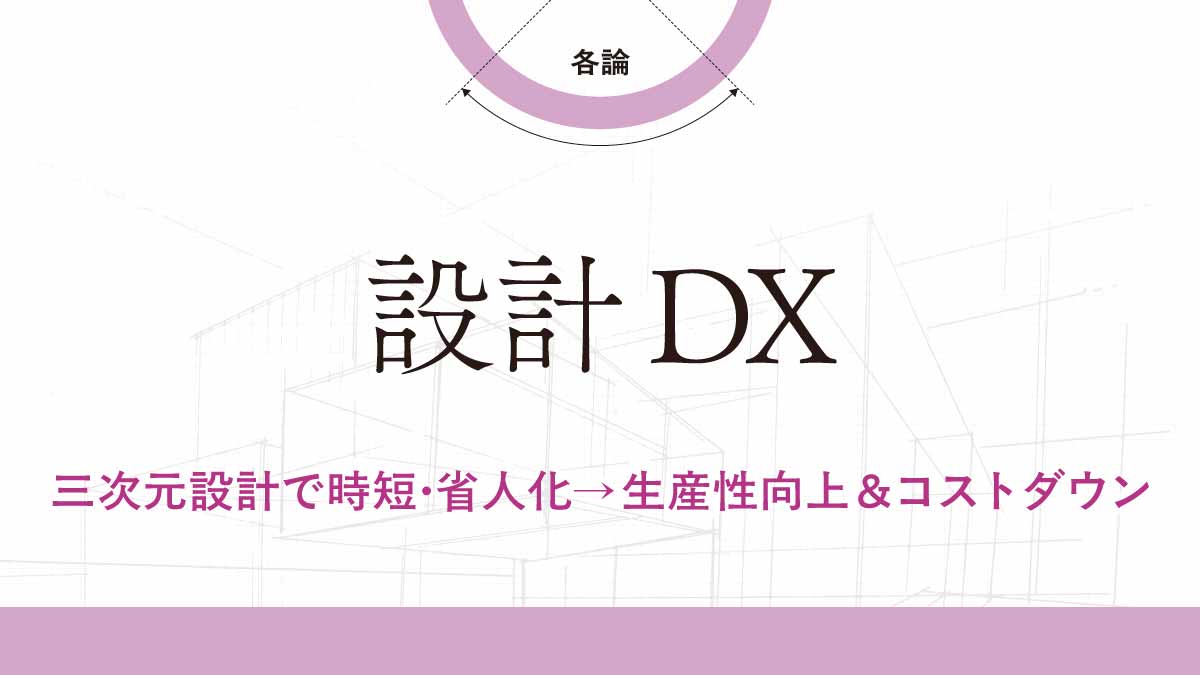
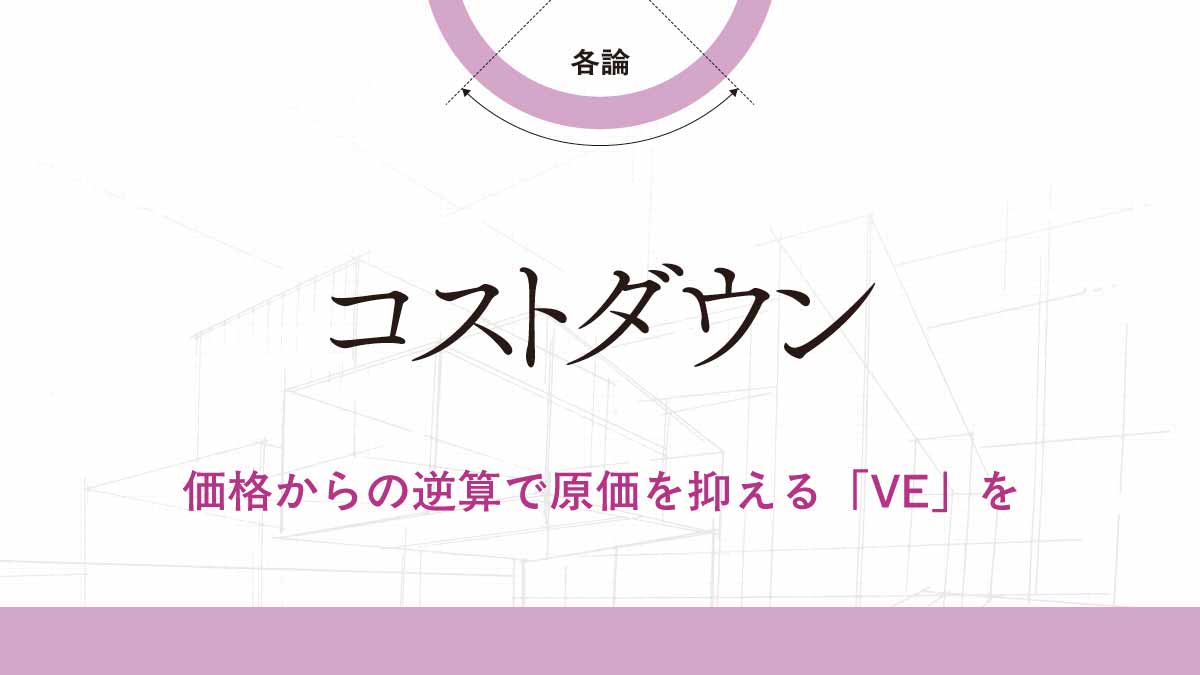
![="住宅ネットワーク[最新]トレンド分析" 住宅ネットワーク[最新]トレンド分析](https://www.s-housing.jp/wp-content/uploads/2025/07/2506_kyo_thumbnail_121.jpg)