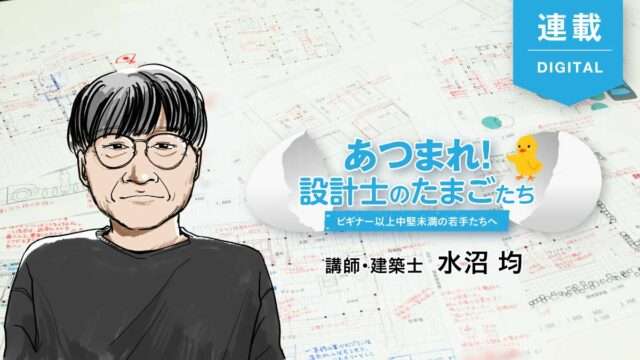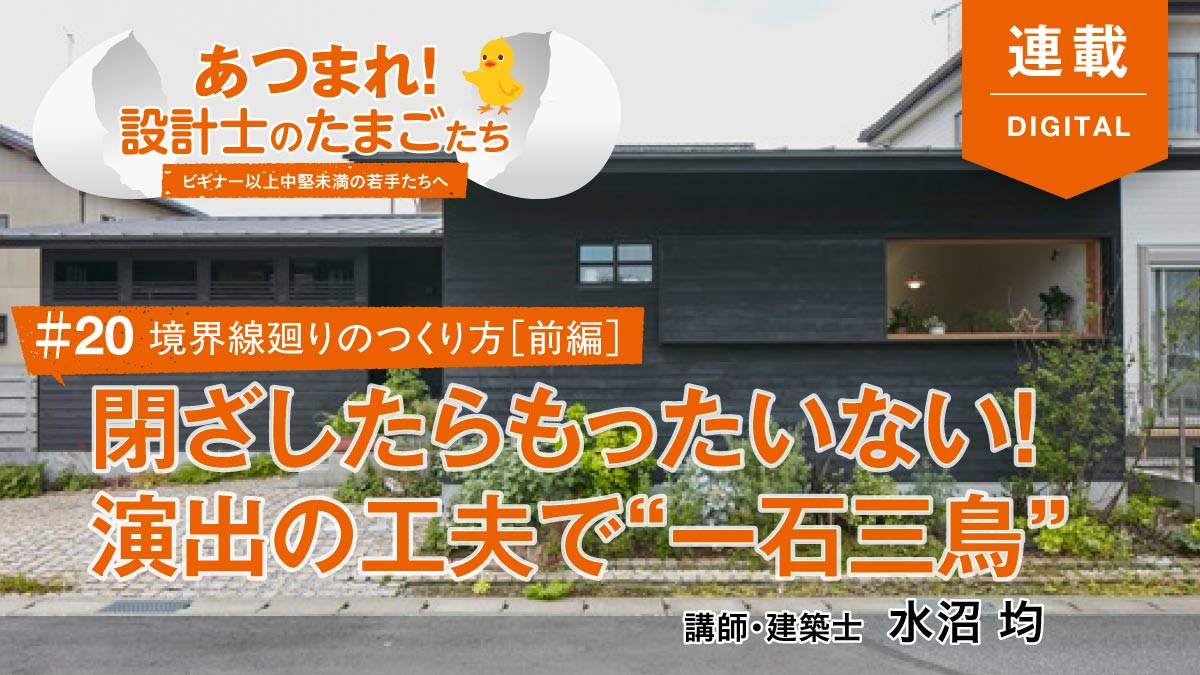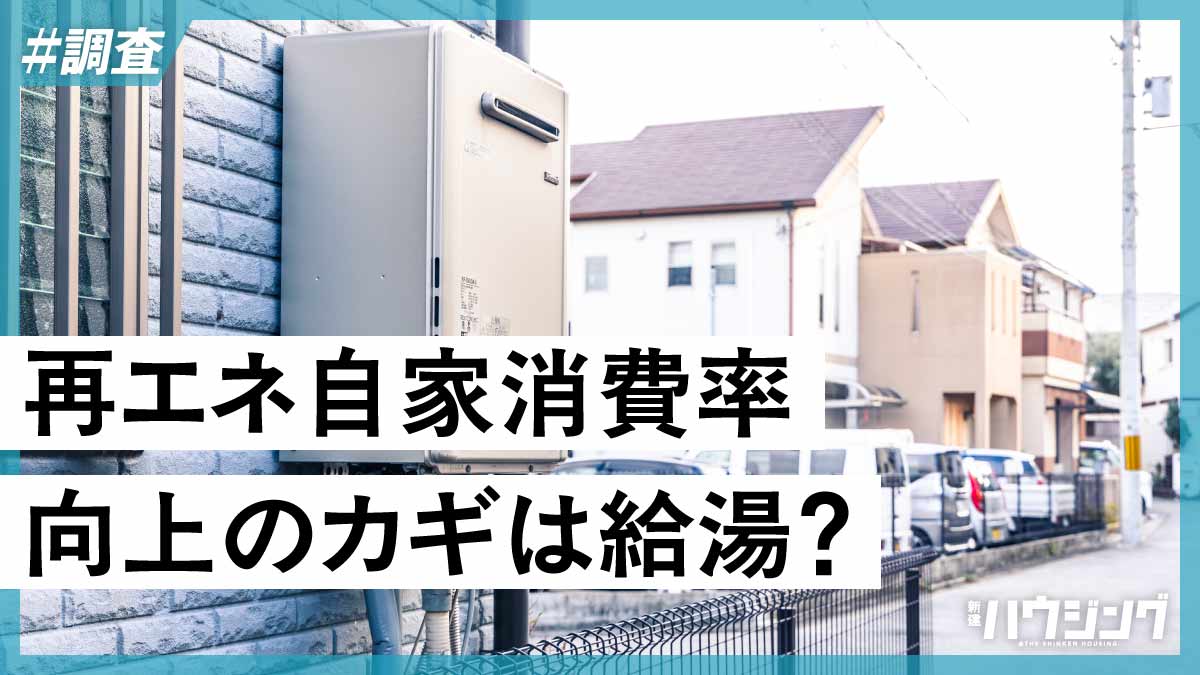若手設計士のみなさんこんにちは。
これまで何度かにわたって窓の魅力をお伝えしてまいりましたが、今回は少し目線を変えて、窓がもたらす光の魅力について考えてみましょう。

光で魅せる演出とはどんなもの?
光の魅力、というとシャンデリアやミラーボールなどの照明効果を思い浮かべそうですが、少し異なります。ここでお話ししたいのは人工光ではなく、窓から入ってくる自然光です。
光そのものは、実は眼には見えません。私たちが見られるのは、あくまでも光に照らされた物体だけなのですね。
ところが窓の設け方や作り方によっては、光そのものを直接眼で見ているかのように味わうことが可能なのです!
ではどのようにして光を見せる演出が可能なのでしょうか。
これには大きく2つの方法があります。1つは、壁や天井などの室内のある部分だけを特に明るく照らし出して見せるという方法。こうしますと壁や天井が光の依り代になって、とても美しく光を見せてくれます。
下の写真は前回記事の最後に紹介したものです。この写真をお見せしたところから、光のお話はスタートしていたんですよね。
窓を奥の壁にぴったり接して設けることで、壁がほかの部分よりも際立って明るく輝いています。壁というよりは、光のスクリーンのようですね。

【写真1】大和の家Ⅱ 設計・礒健介/礒建築設計事務所(写真・礒健介)
そしてもう1つは、窓自体を明るく輝かせてしまうという方法。これは障子窓を思い浮かべていただければいちばんわかりやすいです。障子窓が光で輝いている様子はとても日本的で美しいものですよね。
この方法、単なる透明ガラスの窓では成り立ちません。障子紙を光の依り代にして初めて成り立ちます。
障子窓にしますと外の景色は見えなくなります。が、そのかわりに美しく輝く障子という面状の光を楽しむことができるのです。すりガラスやガラスブロックを用いても同じ効果を期待できます。
このような演出を「透光不透視(とうこうふとうし)」といいます。視線は透けないけれど光は透ける、そんな窓。建築の世界ではわりとよく用いられる用語です。
下の写真は主寝室に障子窓を設けた例です。部屋全体がほの明るく抑えられているのに対して、障子窓がまるで大きな行灯(あんどん)のようにきれいに輝いています。寝室のようにプライバシーの必要な部屋には、このような透光不透視の窓がとてもマッチしていますよね。

【写真2】代官町の家 設計・本田恭平/mononoma(写真・山内紀人)
窓に照らされた一部分がまるで光の塊のように輝く魅力、そして窓そのものが光のスクリーンのように輝く魅力。
今回は前者を、そして次回に後者の例を紹介してまいりましょう。
壁を光の塊のように照らし出す
下のお住まいでは突き当たりの壁を縦長の窓で明るく照ら出しています。ほかの部分と比べると、この壁は光の塊のように室内でひときわ輝いています。
さらに右側の写真をよく見ますと、左側の壁の端部が内側にカーブしていることがわかります。この端部は、窓をあえて視界から隠して光だけを見せる役割を果たしています。美しい光を見せるための優れた造形です。

【写真3(左),写真4(右)】鶴見の家 設計・古谷野裕一/古谷野工務店(写真・西川公朗)※クリックで拡大
同様に、下のお住まいでも正面の壁が美しく輝いています。上の例と同様に、窓の手前に袖壁を設けることで窓を視界から隠し、光だけを見せています。またこの壁は耐力壁としての役割も担っています。構造的な必要性と光の演出とを両立させたすばらしい造形ですよね。

【写真5】北小金の家 設計・礒健介/礒建築設計事務所(写真・礒健介)
天井を照らし出して室内の主役にする光
壁だけでなく天井もまた、光の演出のための優れた素材です。
下のお住まいでは勾配天井の頂部に丸みをつけるという凝ったデザインがなされています。こうすることで天井を照らす光は頂部で折れてしまうことなく、天井全体を美しいグラデュエーションで照らし出してくれています。まるで天井がうねって浮遊する光の塊のようです。


【写真6(上),写真7(下)】清眺台の家2 設計・本田恭平/mononoma(写真・山内紀人)
下のお住まいはRC造ですが、高窓の光に照らされた打ち放しコンクリートの天井面と壁面がなんとも美しいと思いませんか?コンクリートという素材の重量感を光が柔らかく照らし出して、独自の存在感をもたらしています。
窓はあくまでも光を導くための道具で、コンクリートの天井と壁すらも光に形を与えるための依り代に徹している、明快で強い説得力を持った造形です。

【写真8】小石川の家 設計・森田葵/あおいも(写真・森田葵)

【写真9(左),写真10(右)】小石川の家 設計・森田葵/あおいも(写真・森田葵)
床を照らし出す伝統的な光
壁を照らす光、そして天井を照らす光を見ました。では次は? そう、床を照らす光。この光、実は奥がとっても深いのですよ。
下の2つの和室では障子窓が床を明るく照らしています。床は明るい色合いの畳敷き。一方、天井や壁はむしろトーンを落としています。伝統的な和風の造りですよね。
このような演出は、実は日本の昔からの住まいの大きな特徴です。和室でいちばん明るくしたいのは床。そして天井や壁は畳からの反射光でほの明るく照らされていればよいのです。
昔の日本では夏の日差しを避けるために、窓の外に軒が深く出ていました。そして軒裏は明るい色合いで造られました。こうしますと地面に落ちた日差しは軒天井に反射されて、室内の畳を照ら出します。したがって部屋を明るくしたければ床を明るい色合いにするとよい。そうすれば今度は床が光を反射して、部屋全体を照らし出してくれます。畳が明るい色合いをしている理由の一つですよね。日本の家屋は古来このようにして室内を照らしてきたのです。
部屋全体を光の箱にしてしまう
最後にお見せするのは部屋全体が光に包まれた、光の塊のような作例です。
下のお住まいには家の中央に階段室がありますが、円筒形の螺旋階段室の上部いっぱいに天窓を設けています。


【写真13(上),写真14(下)】さがみ野の家 設計・礒健介/礒建築設計事務所(写真・西川公朗)
こうすることで、部屋の中央に大きな照明器具が置かれたような個性的な階段室になりました。部屋の奥の方は暗くなりがちですが、たちどころに明るい奥ができあがりました!
さまざまな光の魅力、いかがでしたでしょうか。建築とは極端に言えば閉じた箱を作る作業ですが、そこに穿たれた窓はまさに光のドラマの演出家なのです!
次回はもう一つの光の魅力「透光不透視」をお話しいたしますね。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。