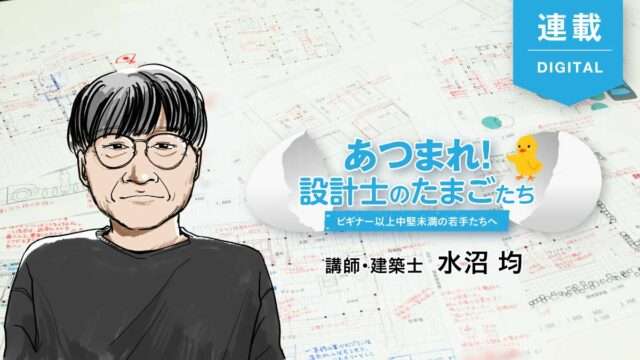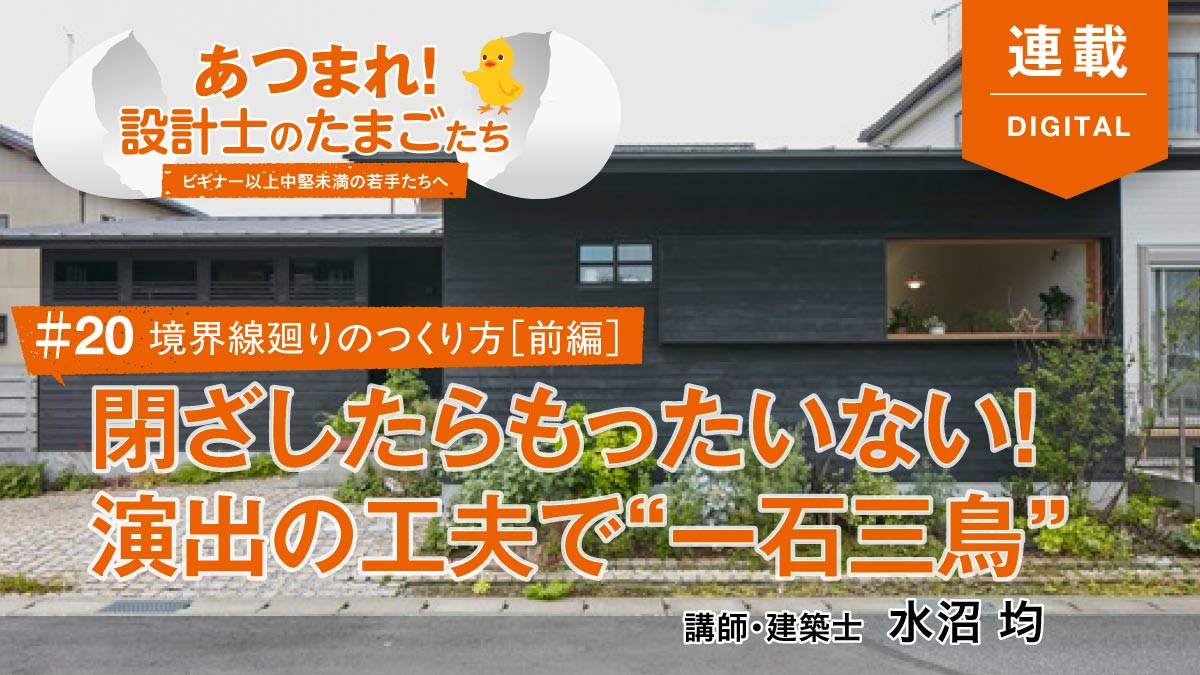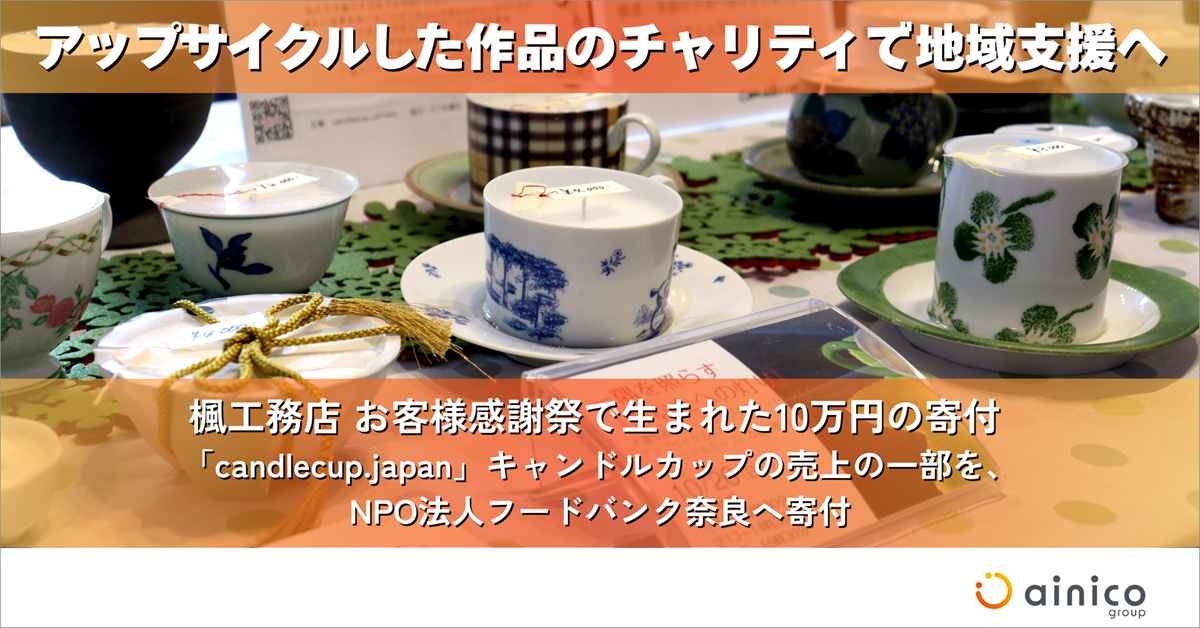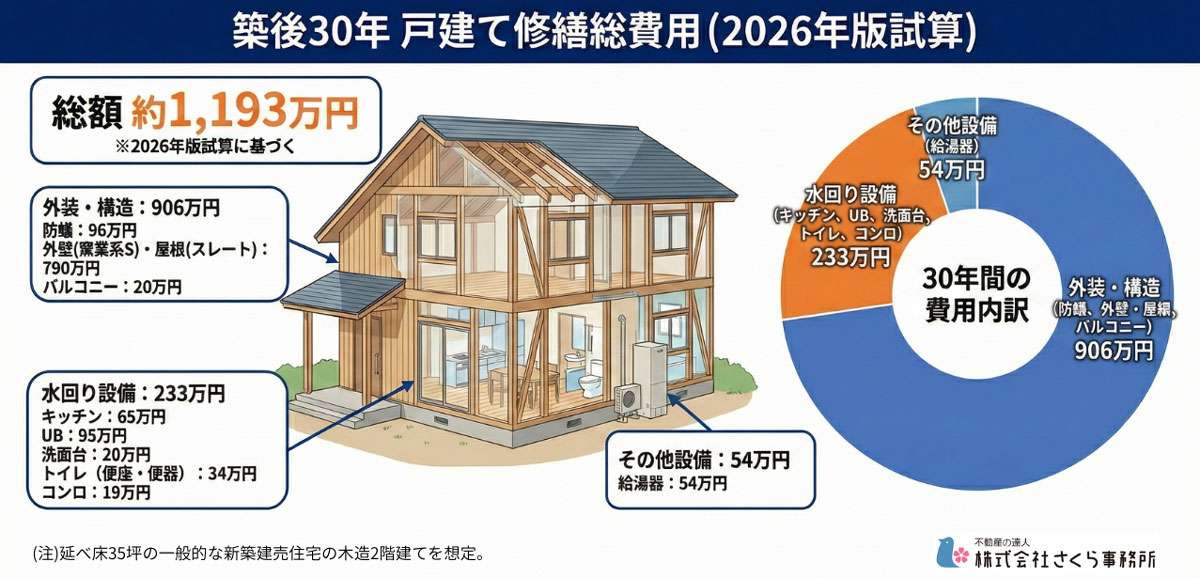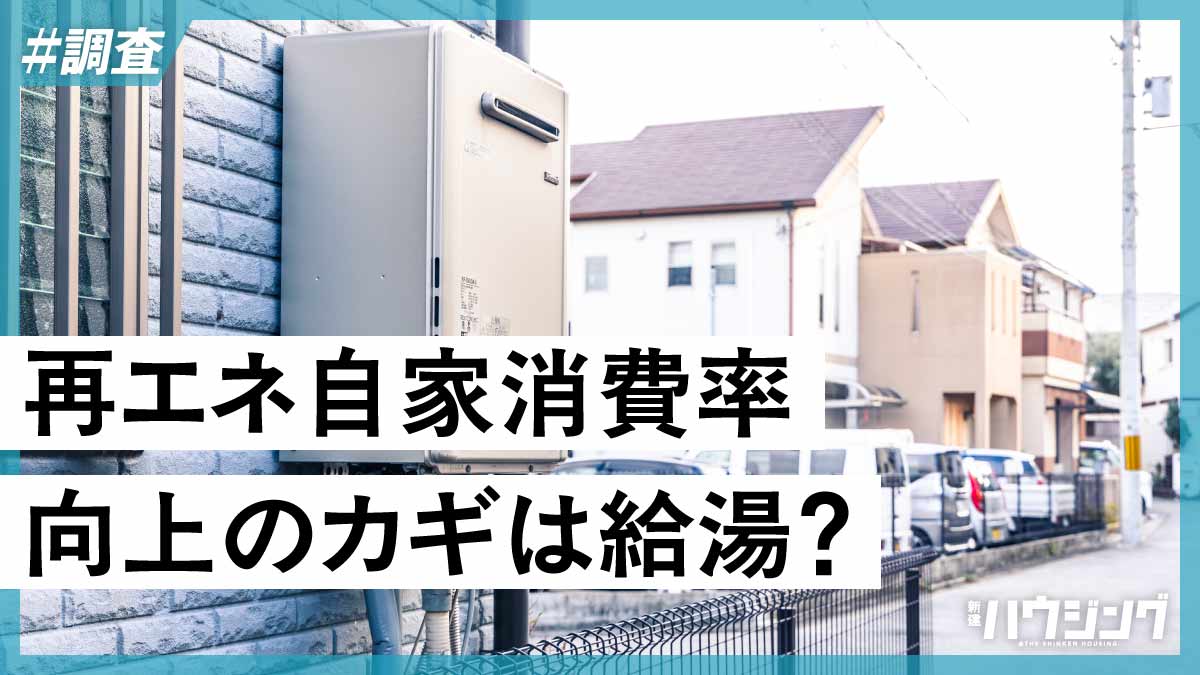若手設計士のみなさんこんにちは。
前回の吹き抜けに引き続いてタテのつながり第二弾、今回は階段を見てまいりましょう。
階段は住まいの中で唯一、タテ方向に移動することのできる場所です。平らな床ばかりの室内にあって、実は階段はとても異色な存在なのです。
一般に住まいの下階と上階は、吹き抜けを設けなければほぼ分断されてしまうのが普通のこと。けれども家族のためのせっかくの住まいです。できたら下と上とをもっともっとつなげてあげたいですよね。
そんなとき、階段は唯一のタテ要素として力強い存在になってくれるのです。

光を下階に導く光井戸としての階段
階段は人を上下に導くだけでなく、光をも下階に導いてくれます。例えば周囲が建て込んでいて1階に大きな窓を設けづらいとき、上階に設けた大きな窓からの光を階段がたっぷりと下までもたらしてくれます。まさに光の「井戸」ですよね。
密集地に住まいを計画することがあったら、ぜひ光の拠り処として階段を考えてみてください。暗くなりがちな1階がむしろドラマチックで魅力的な場所になってくれます!
下の住まいの階段はまさに光井戸です。階段と一体で吹き抜けも設けて、下階を明るく照らし出しています。
階段は細い部材で組める鉄骨材を採用しています。こうすると光の豊かなボリュームがますます体感できますよね!



【写真1,2,3,4】桜花のいえ 設計・工藤健志/建築設計事務所RENGE
下の住まいでは光井戸の存在感をさらに強調しています。住まいの奥にあって本来なら真っ暗になるはずの場所に階段を設け、上階から思い切り自然光を浴びせて下階を照らしています。
さらによく見ると、すぐ横のキッチンには壁で閉じてあえて照らさず、奥にある別の開口からの明るさをキッチンで味わってもらうという凝りよう。光を活用して造形に生かす手腕が見事に発揮されています。


【写真5,6】鶴見の家 設計・古谷野裕一/古谷野工務店(写真・西川公朗)
また下の住まいでは、光井戸としての階段をまるで芸術作品のように美しく演出しています。
天井の奥にハイサイドライトを設け、そこからの光で垂れ壁を照らし出しています。光源の窓はあえて見せずに奥に設けているため、まるで天から降ってきたような光を味わうことができます。
そう。階段にはこんな芸術作品のような造形だって可能なのです。

【写真7,8】碧海の家 設計・藤井雄一朗/アルヒフト建築研究所(写真・山内亮二)
住まいのメインストリートとしての階段
さて階段がそれほどまでにすてきな存在なのならば、端っこでなくいっそ住まいの中心に持って行きたくなりますよね。どんどん持って行きましょう!第一その方が便利ではありませんか。どの部屋にもすぐ行けるし、住まいという小さな小さな「街」の中のタテのメインストリートにもなってくれます。
下の住まいは以前にも一度紹介しましたが、まさに階段が住まいの中央に設けられています。
そして中間階にも場所があったり、階段に面して外の場所まであったり、この住まいのすべての場所にこの階段で出会うことができるのです。なんて楽しい階段、楽しい住まいでしょう!


【写真9,10】千川の住宅 設計・織田遼平/織田建築設計室(写真・下里卓也)
ひそみの場やのぞき窓で階段を楽しく
階段はまた、ほかの場所では得にくい財産を持っています。それは階段下のスペースと、下階と上階との中間地点です。
階段下といえば、収納にして掃除機やゴルフバッグなどを置くのがほぼ定番化しています。けれどもこのような天井の低い小さな場所は、特に子供さんなどがひそんで遊んだりする絶好の場所にもなりそうですよね。
それを活用したのが下の写真左側の住まいです。広々とした吹き抜けの居間の一角に階段がありますが、そこには小さな入り口が設けられて、子供さんのひそみの場になっています。居間が広々して天井が高いだけに、この対比的な小ささは「ひそむ」魅力をますます強めてくれています。私だってここでひそんでみたいです。
また右側の住まいには、階段の踊り場に小さな覗き穴があります。
下階にいる大人の背丈とだいたい同じくらいの高さ。小さなお子さんにとってはとても新鮮な高さのはずです。ここから家族と話したり下階を眺めるひとときは、きっとお子さんにとって宝のような時間になることでしょう。
下の住まいでは踊り場の存在感をグッと強調しています。大きな吹き抜け空間の真ん中に階段を設け、踊り場には手すりを兼ねた大きな幕板を張っています。
ふつうに間取っていると階段の踊り場は自然と奥に配されて、目立たない存在になります。けれどもこの住まいのように室内の主要な部分に面して階段を設けることで、踊り場の持つ豊かな立体感を活用することができるのです。

【写真13,14】東大宮の家 設計・中島行雅、古谷野裕一、森田悠紀(写真・西川公朗)
階段の美しさを見せてしまおう
階段は住まいの中で数少ない斜めの形をした要素でもあります。そこには段々がついたり、模様のような手すりもついています。
ならばいっそ、これをオブジェのような美しい造形物として作り上げて、部屋から鑑賞させてしまいたくなりますよね。そんな例が下のすまいです。

【写真15,16】笠松の家 設計・本田恭平/mononoma(写真・野村宜弘)
階段だけが持つ「斜め感」がとても強調されていますよね。ささらを鋼材で作り、木製の段板をサンドイッチしています。ささらは木製だとどうしてもゴツくなってしまうけれど、鋼材ならば薄く小さく軽やかに作れます。素材レベルまで磨き上げられた珠玉の階段ですね!
階段は壁で囲んで「階段室」として密室化させてしまうばかりではもったいない。こんなすてきな階段もどんどん作りましょう。
さてさて、2回にわたって住まいのタテの場所づくりとつながりを考えてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。住まいの魅力が持つ膨大な可能性の一端に少しでも触れられたら幸いです。
それでは次回をお楽しみに!
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。