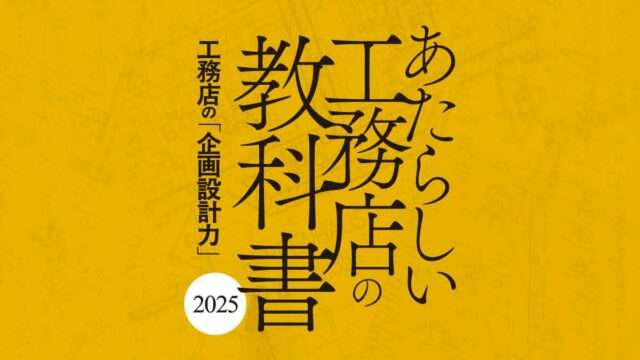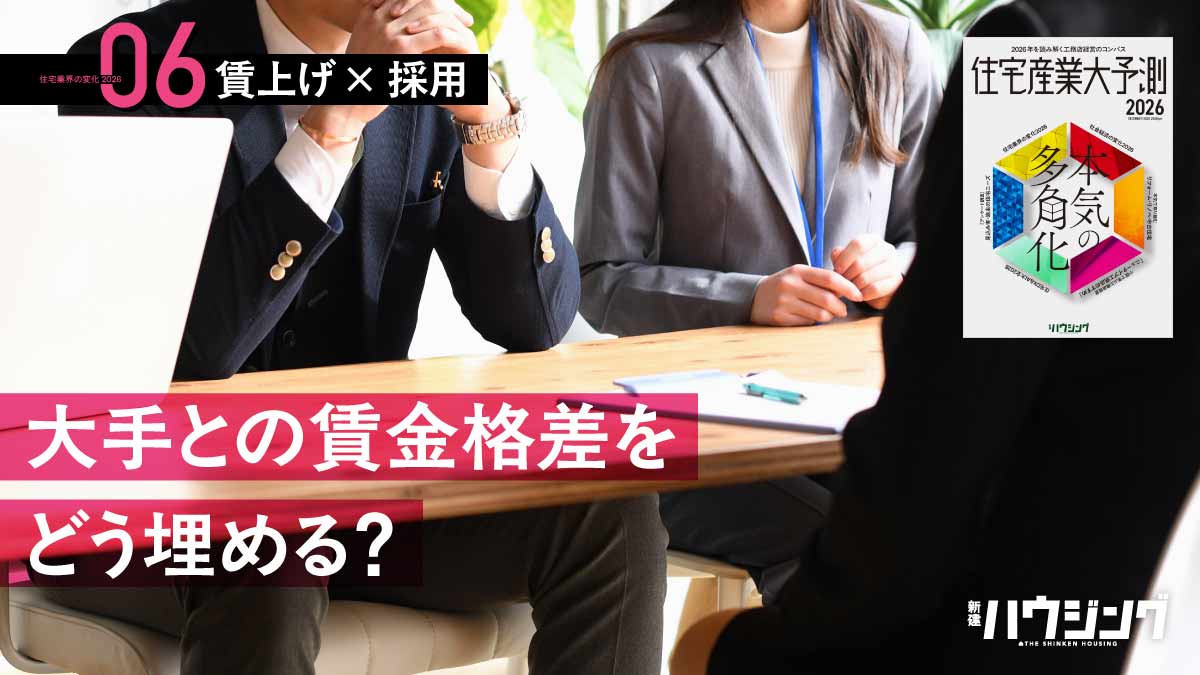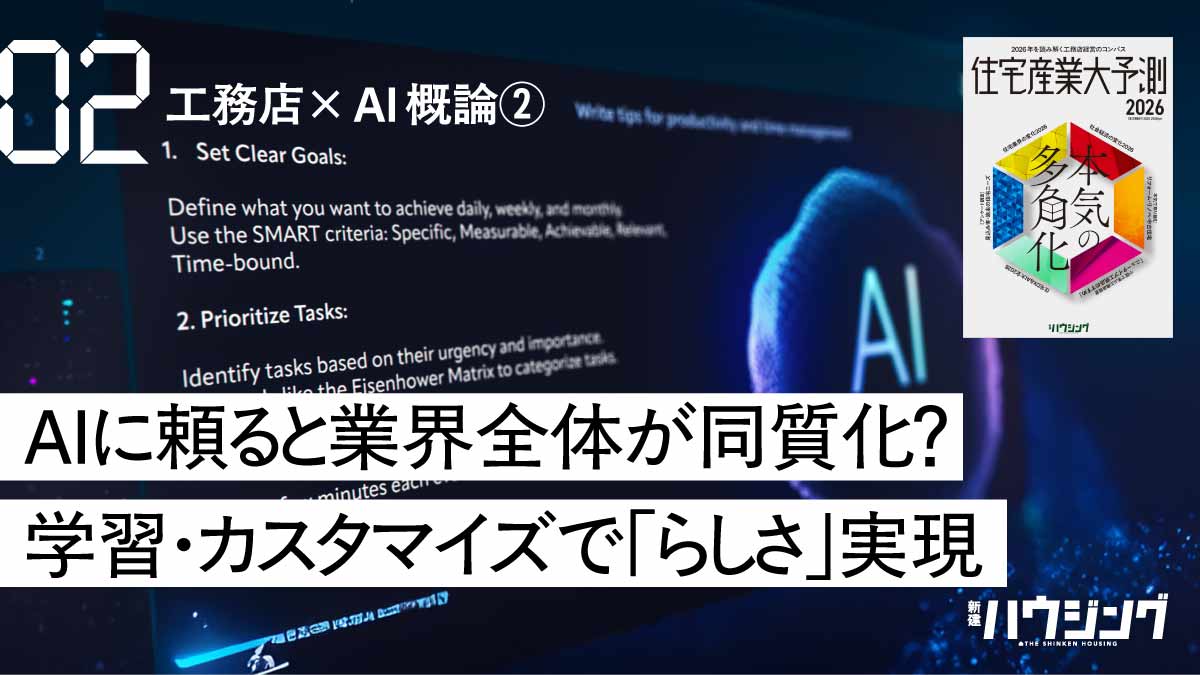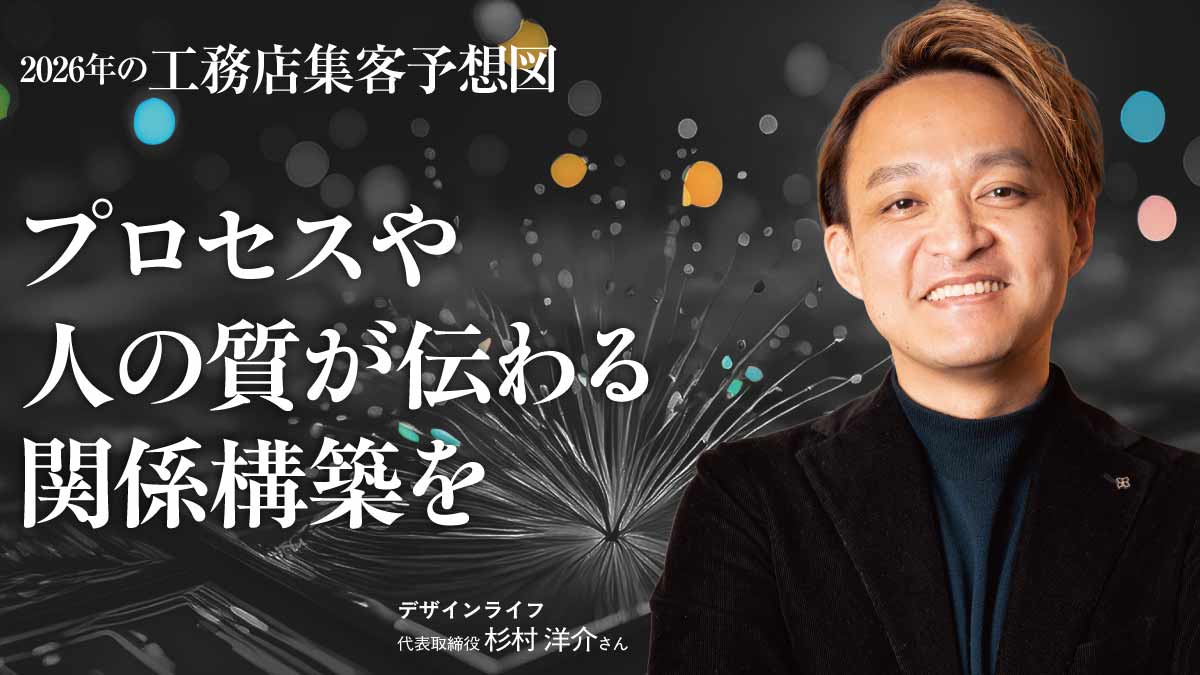住宅業界は性能向上を進めてきたが、国の市場調査から見えてくるのは性能と並んでデザインが重要だということ。結局建主がほしいのは今も昔もデザイン・構造・断熱を「全部取り」した住宅だろう。弊社もずっと「全部取り住宅」をつくり続けているが、UA値0.3以下で長期優良住宅、耐震等級3といった事例が増え続けている。ドイツのパッシブハウス基準の住宅も4軒設計した。
構造や断熱のせいでデザインが良くなることもなければ悪くなることもない。
間取り優先の弊害
私は大学や新建ハウジング主催の工務店設計塾などで設計を教えているが、どこでも最初に伝えているのは「設計手順の見直し」だ。
大半の設計者は方眼紙に間取りを描くことから設計を始める。私の場合、まず描くのは屋根や中間領域の形。そこから真っ先に検討を始める。
その理由はウチとソトの境界部のデザインが建築にとって一番大事だと考えているからだ。国内外の優れた建築を見ると境界部に建築としての魅力が凝縮していると感じる。だが大半の設計者は豊かなウチ・ソトの境界をつくることよりも、部屋数とか家事動線や収納、建主の要望に応えることを優先しているはずだ。
また、間取り優先で後付けした立面は絶対に格好良くならない。間取りを優先すると上下階の力の流れがあみだくじ的になって無駄な天井懐が必要になる。要は性能が悪くなる。
建主から食品庫、ファミクロ、シュークローク、室内干しスペースを求められることが増えていると思うが、これらに面積を取られ肝心のLDK、人がいるスペースが半分以下になっていないか。生活を楽しめないレベルまで生活のメインスペースが狭くなるのは本末転倒だろう。
建築に要求される3つの条件は「用・強・美」とされるが、間取り優先で設計するとすべてが望ましくない家になりかねない。
まず屋根の形を決める
私が考える理想的な進め方は以下の通りだ。
準備として使う構法や素材をあらかじめ決めておく。類似事例を調べたうえで物件のテーマを見定め、与条件を整理する。
設計に入ったら、まず屋根と中間領域を考え、窓と架構を整理してから、最後に間取りをつくる。間取りを最後に考えるのがミソだ。
住宅の平面はほとんどの場合長方形なので、屋根の形を決めること=全体の形状を決めることだ。周辺環境を考えながら、最初に屋根と建物全体の形を決めたい。
同じ間取りでも様々な形の屋根をかけることができる。さらに軒の出、勾配、高さなど屋根には無数の選択肢があり、自由度が非常に高い。設計者のオリジナリティが最も発揮できる部分だ。そもそも・・・
続きは「あたらしい工務店の教科書2025」P.74〜でお読みいただけます。
\あたらしい工務店の教科書2025・まとめ買いはこちら/
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。