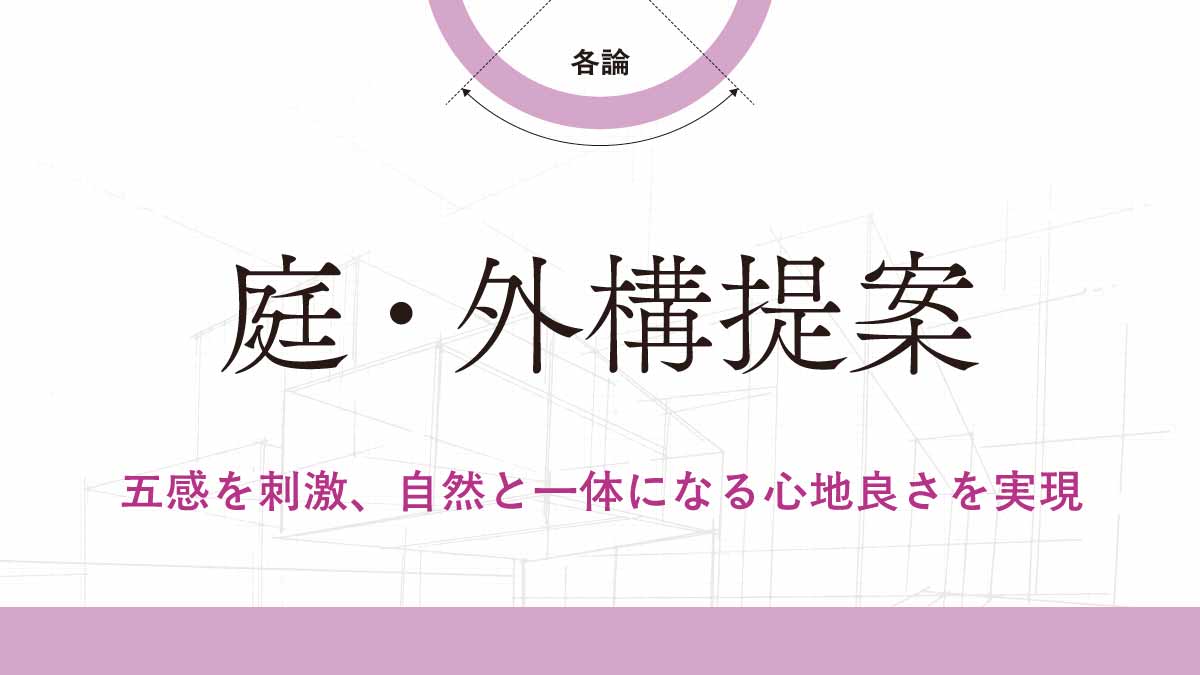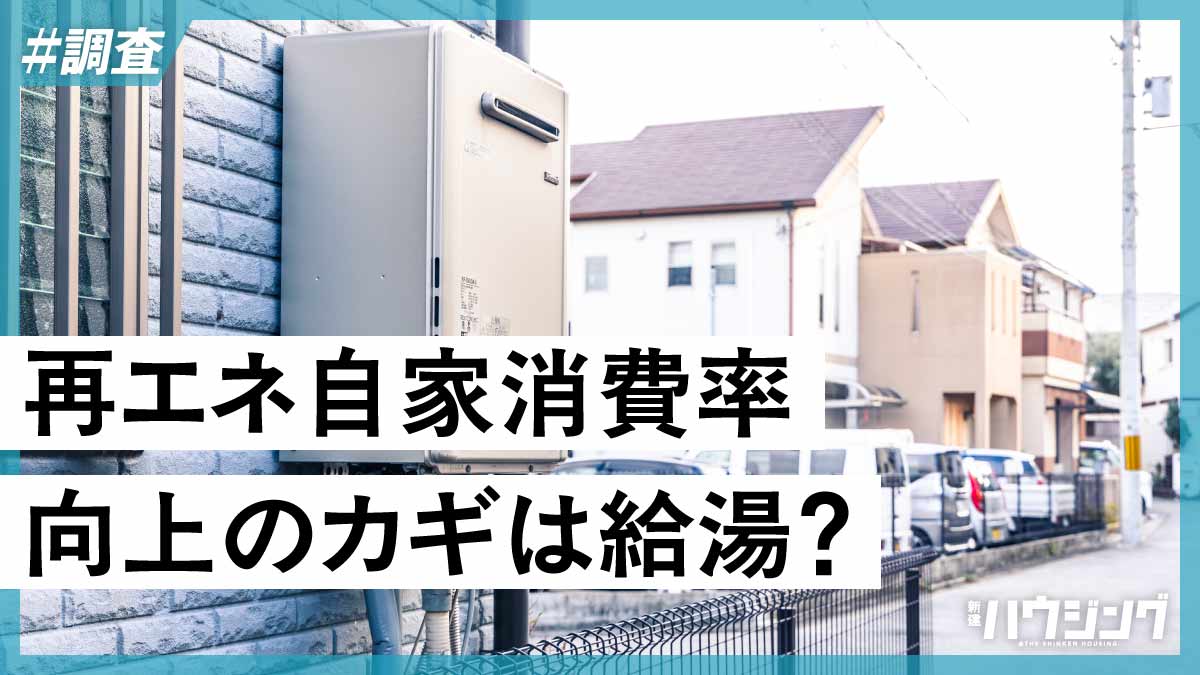変わる注文住宅市場
平成25年に約35.5万戸あった持家(新築注文住宅)の新設住宅着工は、令和6年には約21.8万戸と、約4割減少した。
世帯の平均人数は2.23人に減少。それに伴って持家の平均面積は約114㎡に減少。平屋率も15%に上昇、九州をはじめエリアによっては半数前後が平屋になっている。
資材インフレが定着、首都圏の注文住宅平均価格は3943万円、首都圏以外でも3264万円に上昇(リクルート2024年調査)。地価も三極化が継続しつつ、人気エリアは上昇。注文住宅は「高嶺の花」になり、注文住宅離れも進む。
こうした市場で生き残るには、規格・セミオーダー・フラッグシップなど価格の層をつくる「多層化」、改修・中古・分譲など事業の柱を増やす「多角化」、そして多層化×多角化を自社らしく統合しスタイル・ブランドに昇華する企画設計力が求められている。
左脳と右脳の融合
縮小する注文住宅市場のなかでもこの10年伸び続けてきたのが高性能住宅だ。だが性能のボトムアップが進み、高性能は標準に、さらには「足切り点」になった。上の図で言えば、性能を中心に「左脳」的価値が強く消費者に受け入れられた10年だったと言える。
すでに「左脳」価値と「右脳」価値を融合して企画設計する時代に入っている。よく言われるのが「性能と意匠の融合」だが、それ以外の融合にも・・・
続きは「あたらしい工務店の教科書2025」P.18〜でお読みいただけます。
\あたらしい工務店の教科書2025・まとめ買いはこちら/
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。


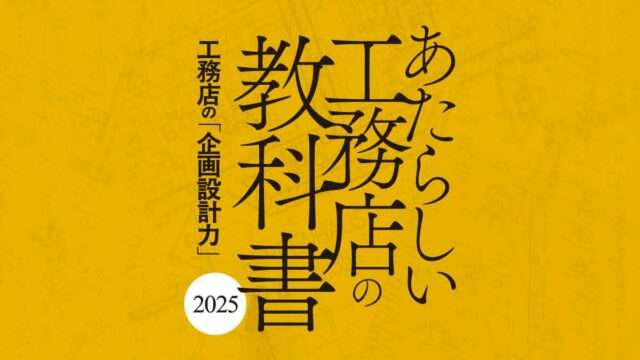

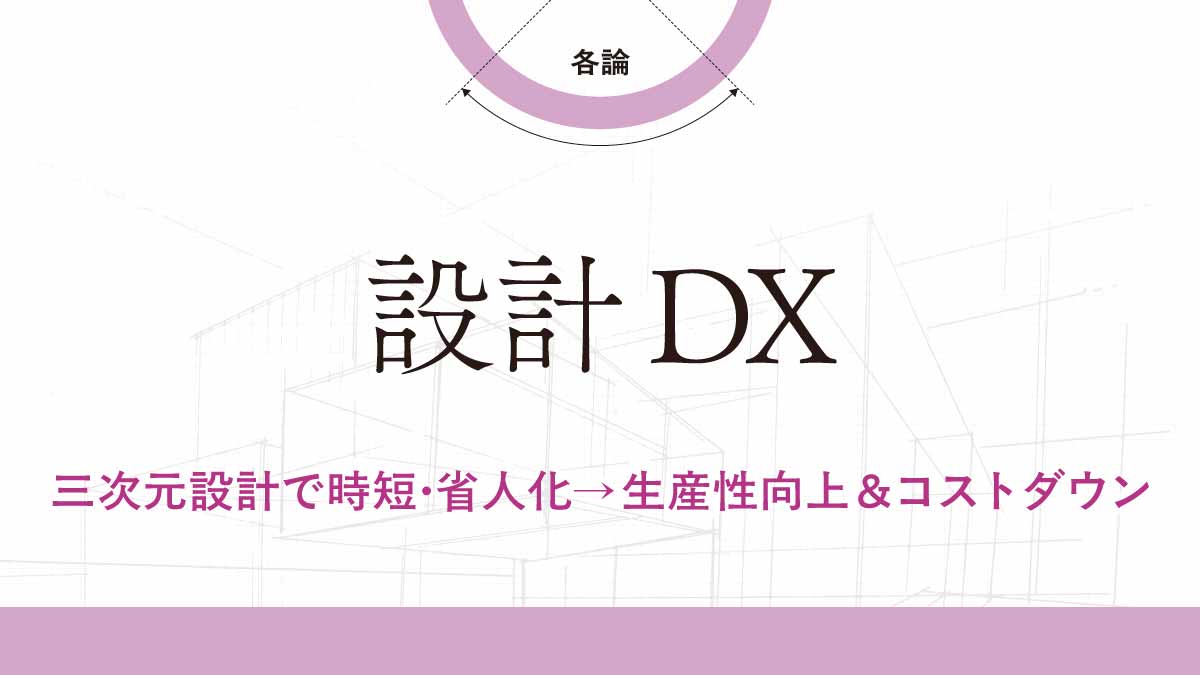
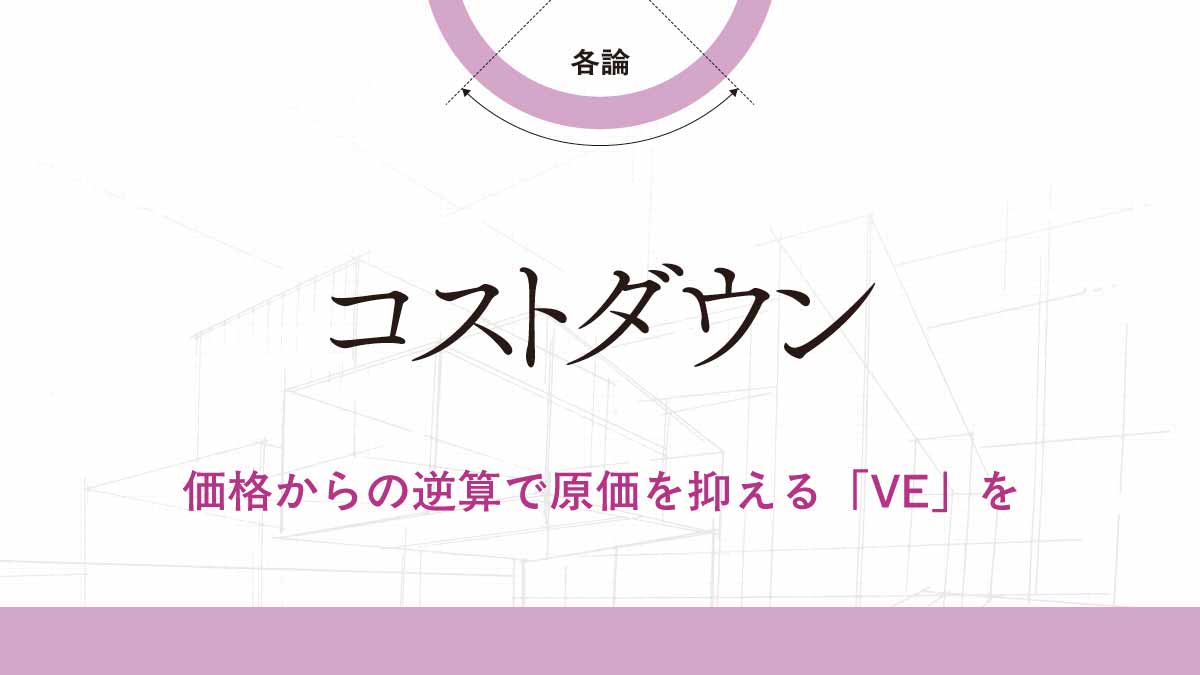
![="住宅ネットワーク[最新]トレンド分析" 住宅ネットワーク[最新]トレンド分析](https://www.s-housing.jp/wp-content/uploads/2025/07/2506_kyo_thumbnail_121.jpg)