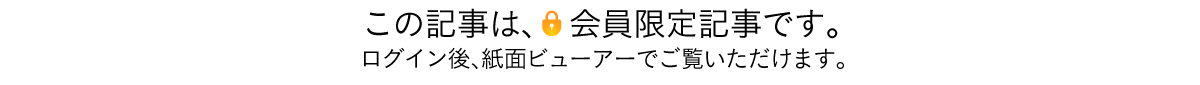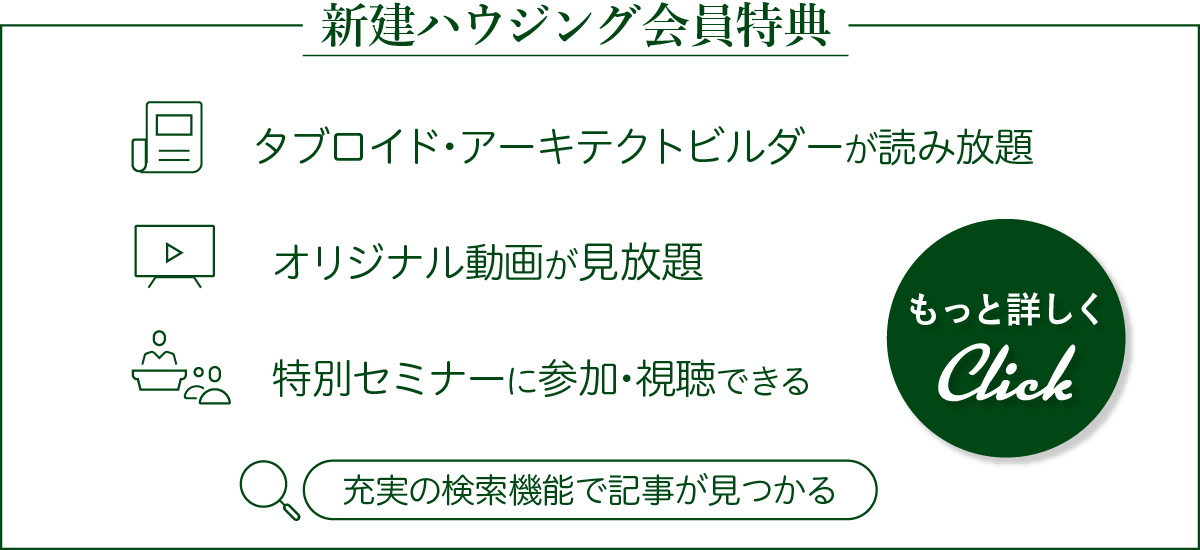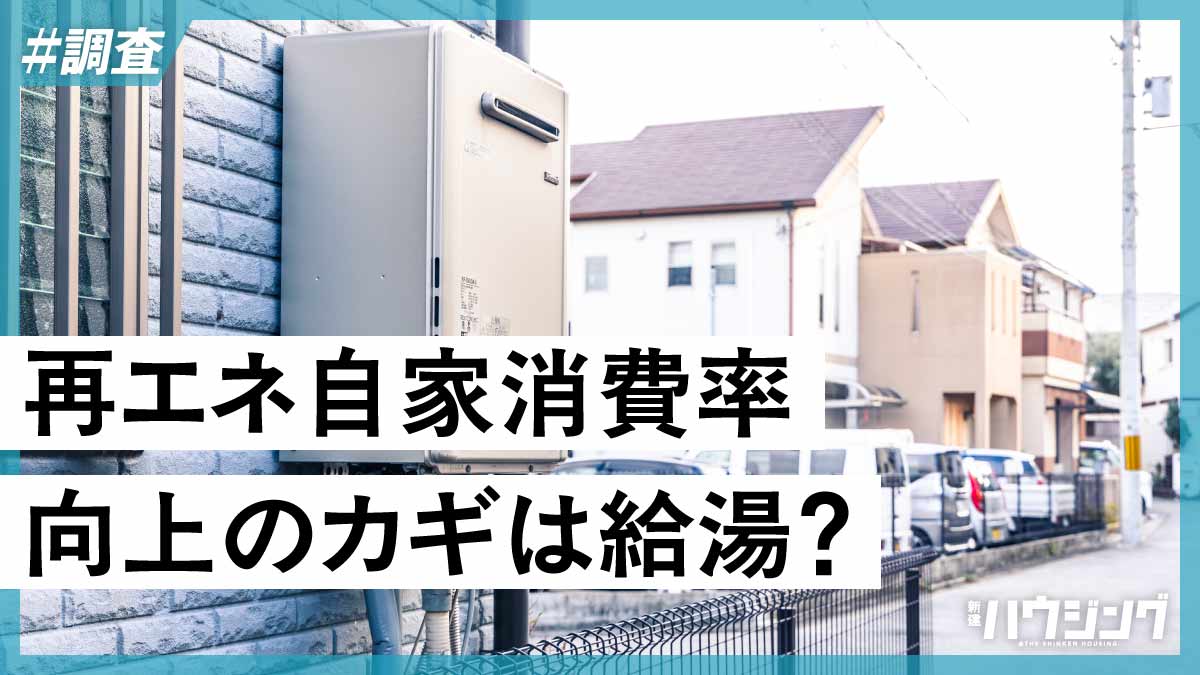確認リノベの需要はあるのか? 対応するための体制や現場の進め方は? 設計はどう考える? リノベ再販の事業性は?といった確認リノベのリアルな手法を実践例から学ぶ。
取材:大菅力 文:大菅力、編集部 取材協力:リヴアース
※本記事は、新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー6月号「確認リノベ超白的Q&A」から、リヴアース(岐阜県養老町)への取材内容を抜粋したものです。
Q. 確認リノベを行う利点はどこにあるの?
A. 性能向上や豊かな空間を実現するにはフルスケルトンが前提になる。確認申請による法的な裏付けを加えることにより信頼性も高まる
ケンジ 新築同等に建物性能を高めて、豊かな空間を実現するのがリヴアースの方針なのか。そのためにはフルスケルトンになることが多いから必然的に確認申請が前提となる。法改正前から法適合調査と同等の現地調査を行っていたんだな
➡︎設計申込時に3〜4人で1時間かけて実測。図面がなくても建物の全体像を復元する
松太郎 これまでの自主検査が法適合調査として制度的な裏付けを得たわけだね。建て主の信頼性がより高まるね。同社は軒裏の防火など細部の性能向上にも地道に対応してきたから、遵法化の設計手法が社内に浸透しているのも強みだね
➡︎法改正により社内の設計スタッフも法令遵守の意識がより強まった
Q. 階段の扱いはどう判断すべきなの?
A. 階段を残してもプランに支障はない。撤去すると間取りと構造が一致しやすくより豊かな空間になる。予算や既存の構造などから判断
ケンジ 同社は階段を残しながらプランを成立させているぞ。階段が中央にある古い大きな家では、階段周囲に回遊動線を設けてまとめる。玄関前に階段がある小さな家だと玄関からすぐLDKに入る間取りにしてまとめている・・・
この記事の続きは、『新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー6月号(2025年5月30日発行)確認リノベ超白的Q&A』(P.53〜)でご覧ください。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。