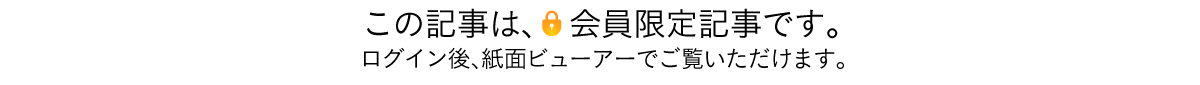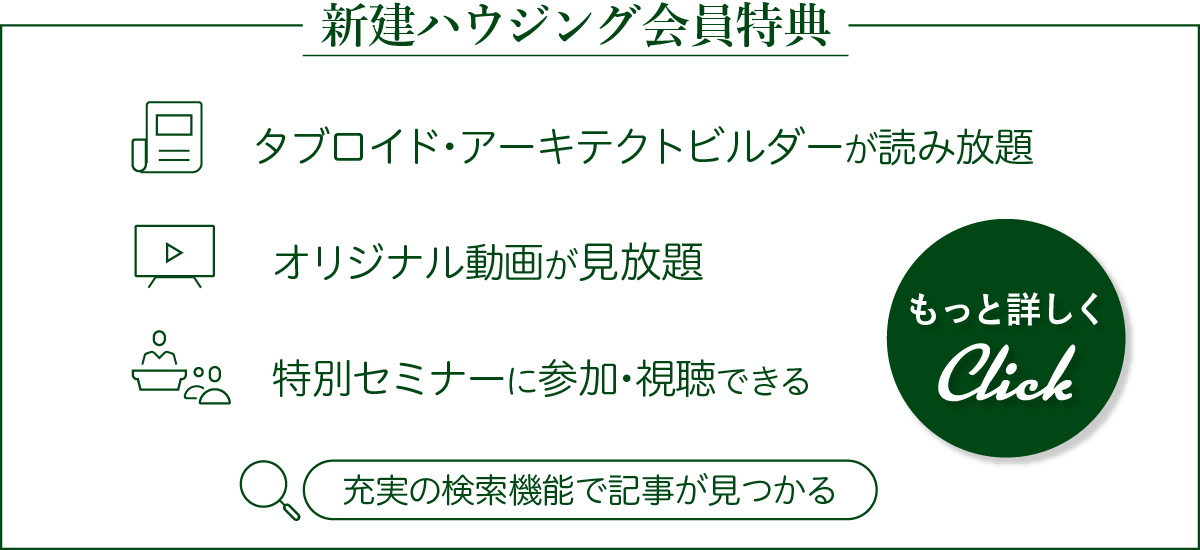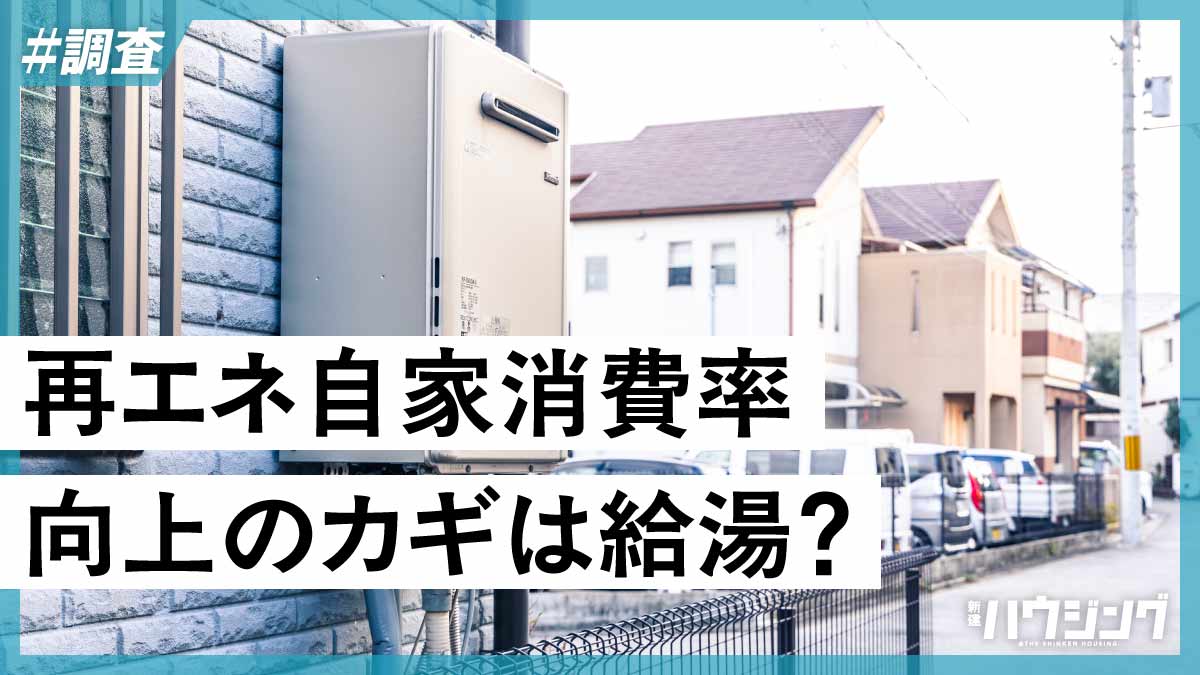確認リノベの需要はあるのか? 対応するための体制や現場の進め方は? 設計はどう考える? リノベ再販の事業性は?といった確認リノベのリアルな手法を実践例から学ぶ。
取材:大菅力 文:大菅力、編集部 取材協力:アイスタイル
※本記事は、新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー6月号「確認リノベ超白的Q&A」から、アイスタイル(兵庫県姫路市)への取材内容を抜粋したものです。
Q.確認リノベになりやすい計画は?
A.二世帯住宅などの実家リノベと太陽光発電の採用。後者の荷重増を評価するには許容応力度計算が求められ、法適合調査の手間も増す
ケンジ 二世帯住宅のフルリノベとか階段が絡むときだな。意外な盲点が屋根に大容量の太陽光発電を載せるとき。屋根が重くなるので耐震補強をして許容応力度計算で安全性を確認するから確認リノベになるな
➡︎壁量計算では固定荷重を評価できないため、太陽光発電を載せての安全性検討はできない
松太郎 許容応力度計算には梁断面や樹種、接合方法の情報が必要だけど解体前には分からないよね。確認申請時は予測で構造計算を行って解体後に再計算して変更届を出す。変更箇所が多いと・・・
この記事の続きは、『新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー6月号(2025年5月30日発行)確認リノベ超白的Q&A』(P.50〜)でご覧ください。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。