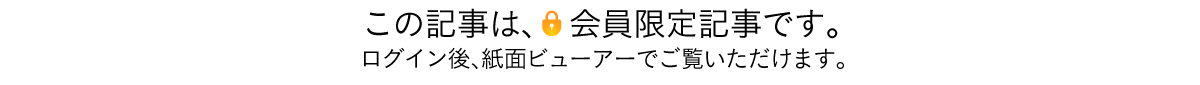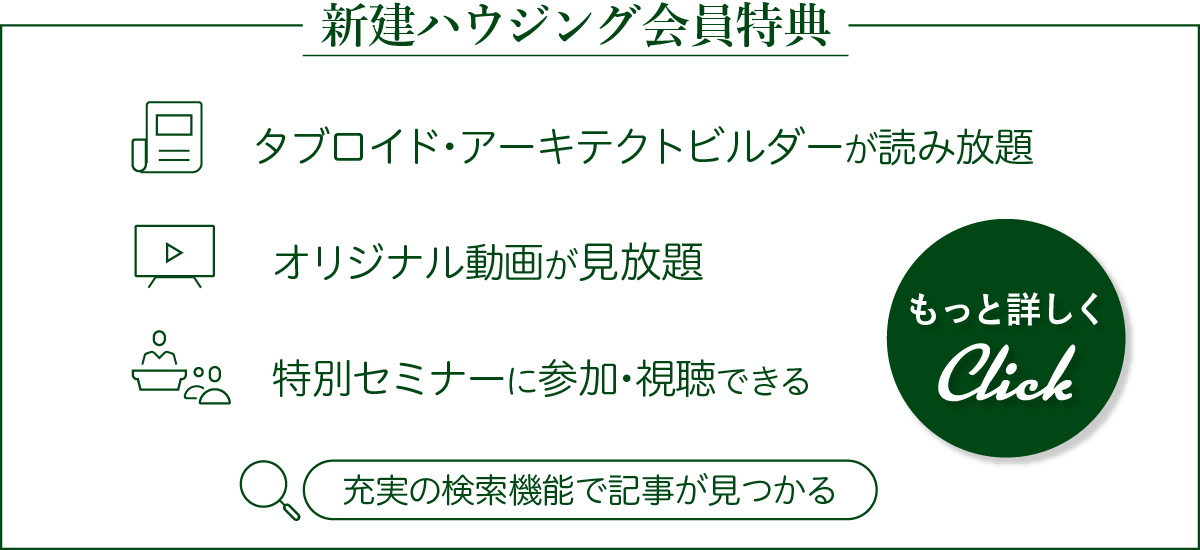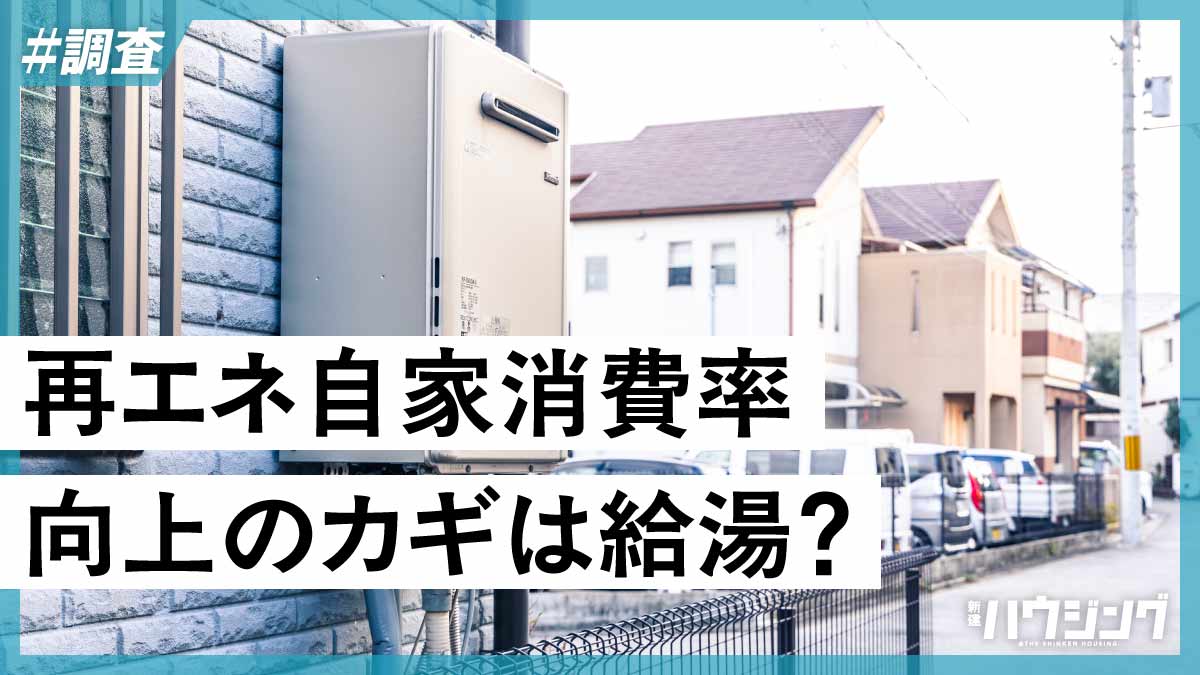既に各地で〝夏本番〟どころではない暑さが続き、熱中症での緊急搬送も週に1万人を超えた。屋外作業が多い家づくりの現場でも、予防に加えて患者発生時、いかに迅速に対応するかが重要になっている。少人数、現場の責任者が常駐していないなど、住宅生産現場の特性を踏まえながら、工務店が取るべき熱中症対策を探る。

総務省消防庁の統計では、6月30日から7月6日の間に、1万48人が熱中症で緊急搬送されている(速報値)。昨年に比べ約2500人の増加となった。近年は自宅で熱中症にかかる人も多く(約4割)、これはこれで深刻な問題ではあるが、工事現場や作業所など職場での発生も未だ1割近くを占めている。
6月1日に施行された改正労働安全衛生規則により、事業者に熱中症対策が義務付けられた。
具体的には、
①熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に「熱中症の自覚症状がある作業者」「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること、
②熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際「作業からの離脱」「身体の冷却」「必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること」「事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地」など、熱中症の悪化を防止するために必要な措置に関する内容・実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること―の2つが事業者の義務となる。
要は患者の発生に備えた体制を整えよ、ということだ。
心理的抵抗や少人数の課題をどうクリアするか
2024年、職場で熱中症により亡くなった人は31人だった(詳細は4面に掲載)。症状が重篤なほど迅速な対応が必要で、意識がない、けいれんが起こっている、といった症状が見られる場合は救急車を要請すべきだと言われている。
しかし、救急車を呼ぶことは大ごとで、騒ぎを起こしたくないという心理も理解できる。また協力業者なら元請けの指示を仰ぎたいと思うかもしれない。心理的な抵抗感で対応が遅れないよう、元請けとしては緊急通報は現場の裁量にすると明確に定めたり、総務など内勤で連絡がつきやすい部署が対応を判断する、といった対策が必要だろう。
また、戸建て住宅クラスの現場だと、1人での作業も珍しくない。2人以上でも、1人だけ2階にいて誰も異変に気づかないようなケースも考えられる。現場監督も、複数の現場を抱えていたりすると1現場への常駐は難しい。施工管理アプリなどDXツールを活用して遠隔で状況を把握してもいいし、定期的に電話などで連絡を取るだけでも違うはずだ。
熱中症を含む労働災害が現場で起これば、元請けの工務店は責任を問われる。施主も・・・
この記事は新建ハウジング7月20日号1〜3面(2025年7月20日発行)に掲載しています。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。