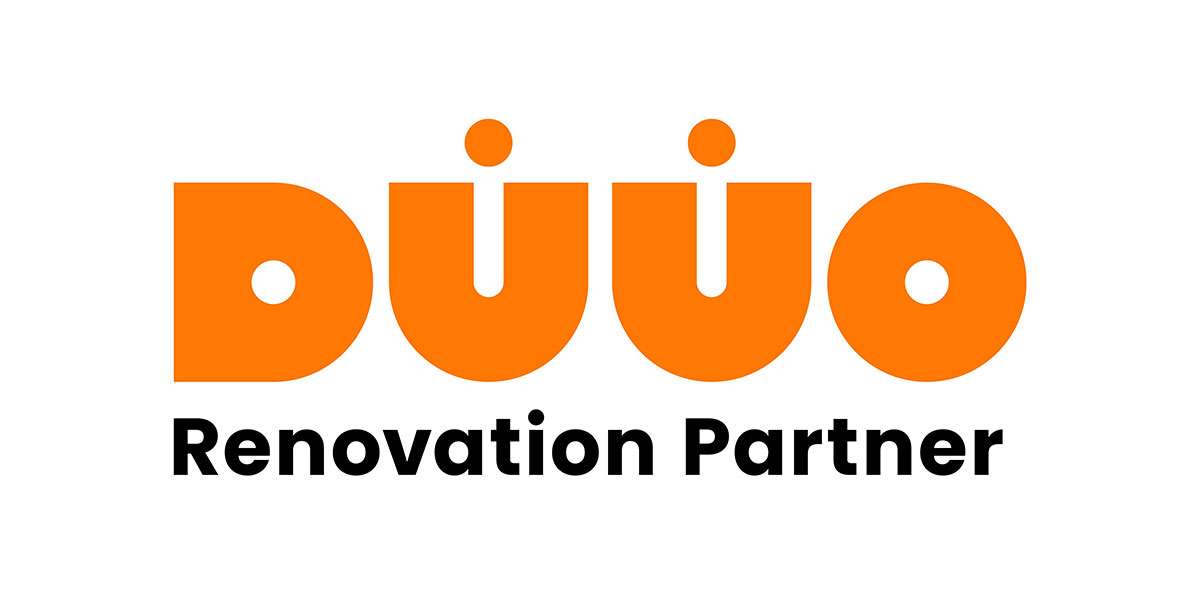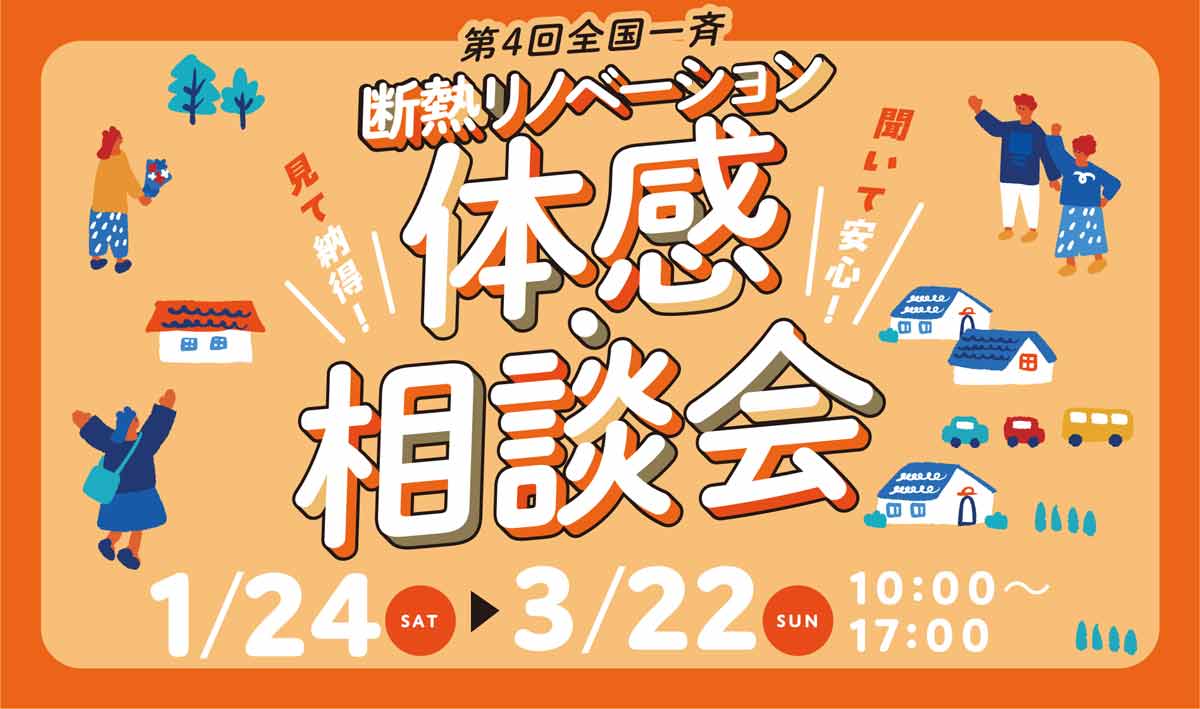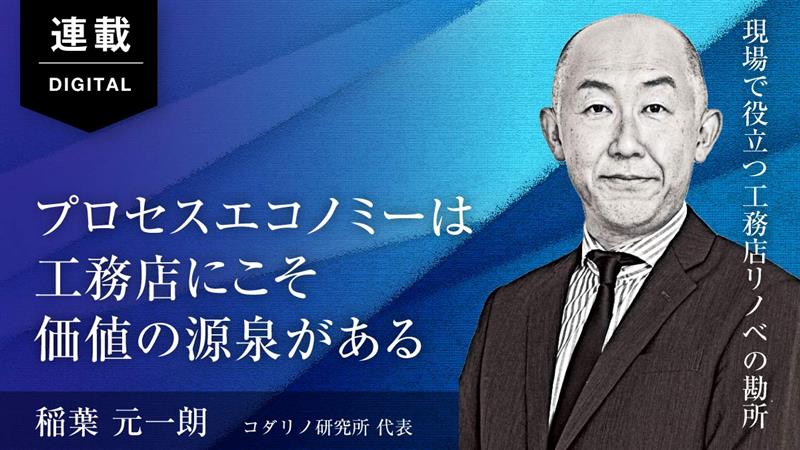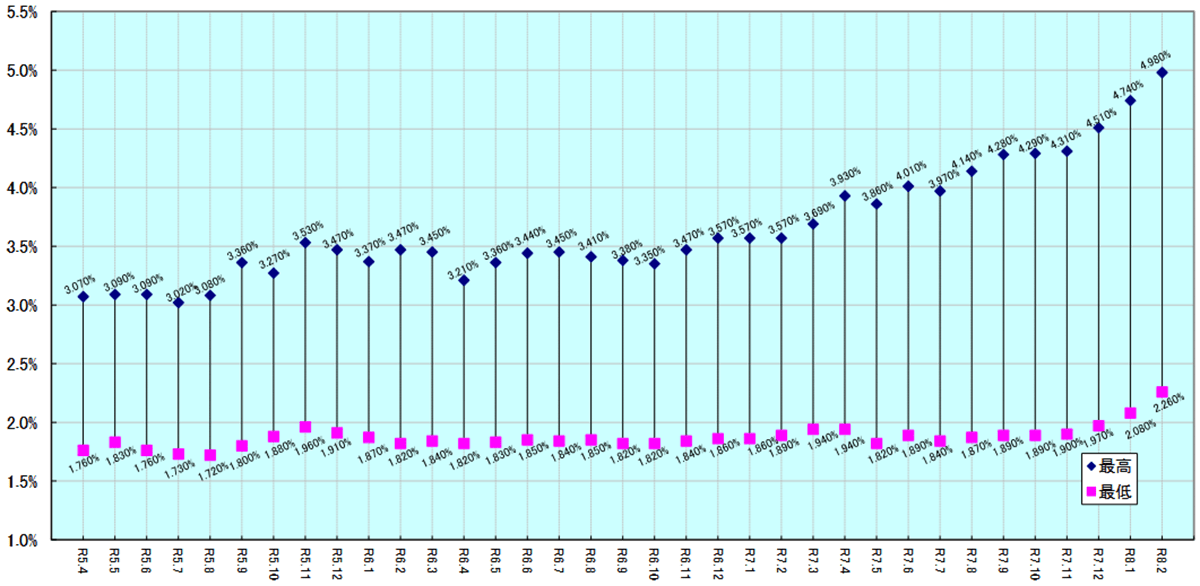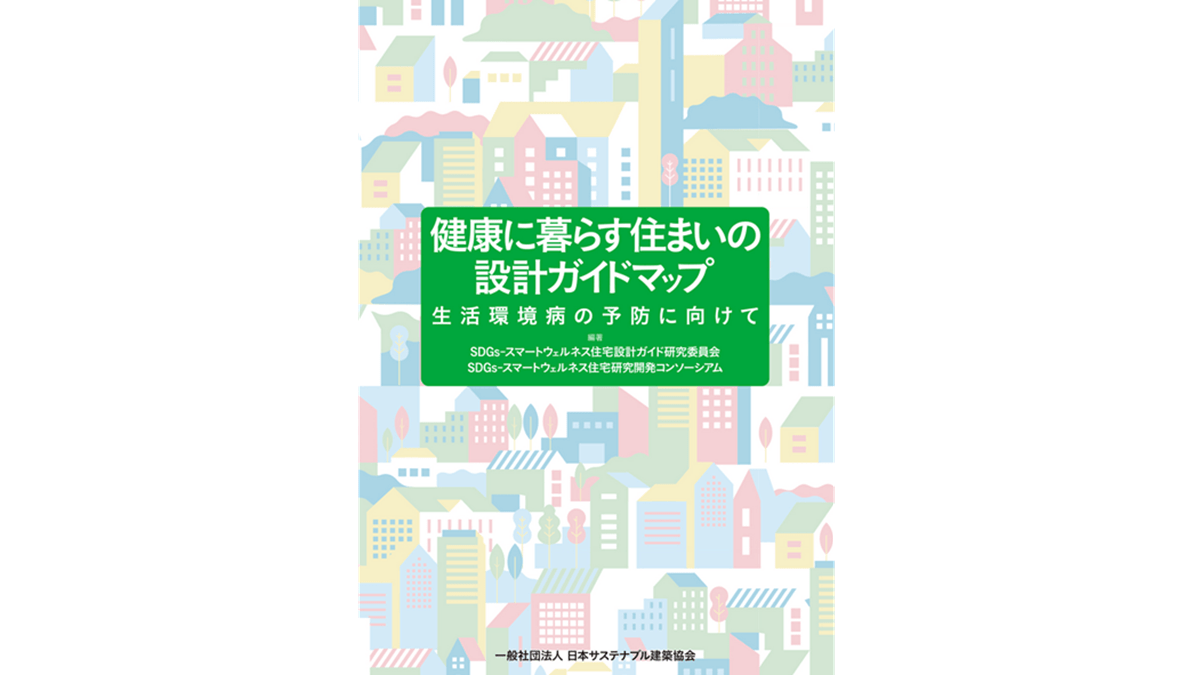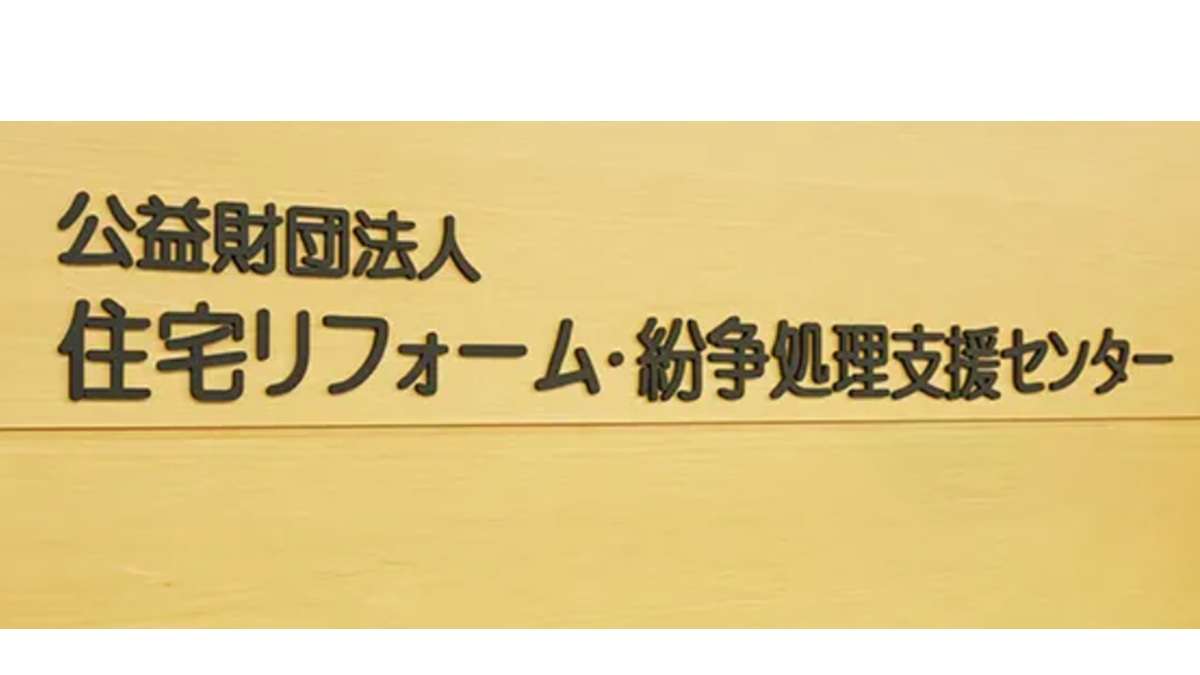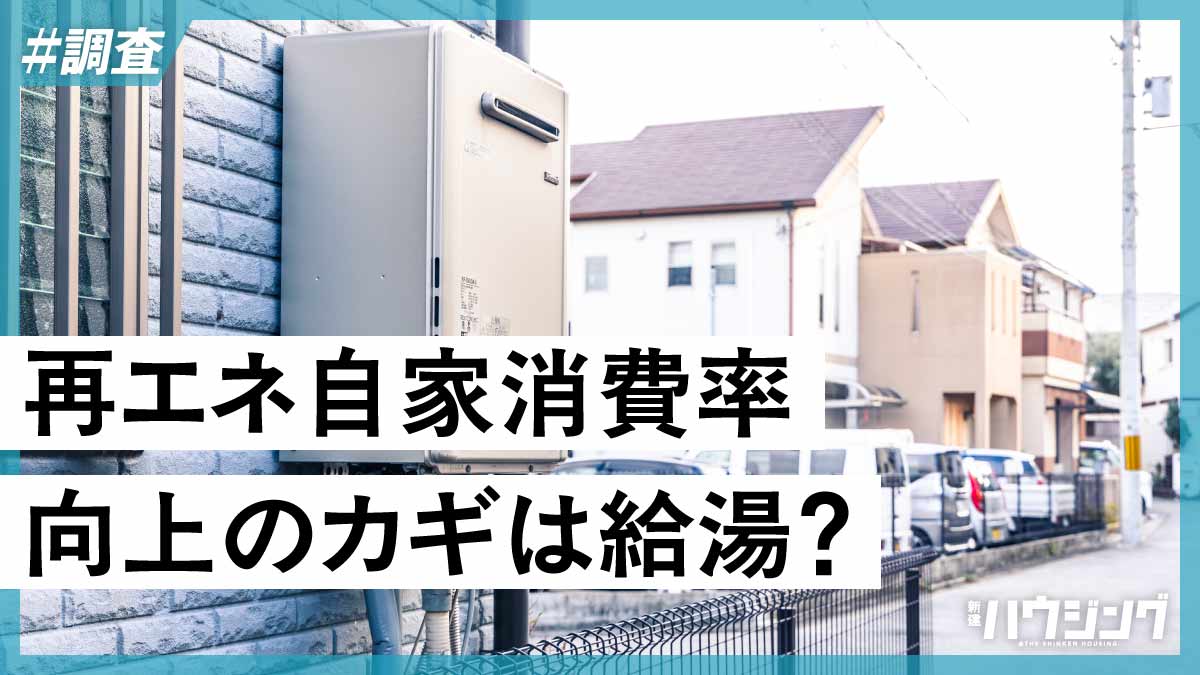この度、新建ハウジング主催のオンライン研修「リノベの売り方講座」でメイン講師を務めさせていただきました。リノベーションに対応する知識や施工力があっても、集客や営業面に課題があるという方々を対象にした講座です。
2024年10月はエコフィールド(強矢到社長)、11月は増子建築工業(増子則博社長)、12月はU建築(三村拓磨社長、小沢健常務)を講師としてお迎えし、全国各地から24社31人の方々にご受講いただきました。
各社のリノベーション事業の規模感を等身大に感じていただいたこともあり、まさにこれから参入しようと目論む中小工務店の経営者、経営幹部が中心で主体的なご質問も数多くいただきました。ご好評をいただきましたので、今回はその振り返りをお届けします。
第1回目:エコフィールド(静岡県富士市)
地域に密着しながら多様なニーズに応えていくため、持ち家リノベを主対象にしながら、中古+リノベ、買取再販的な要素も取り入れて展開しています。リノベーションのフルライン化ができつつあるのは、顧客ニーズに応えるアーキテクトビルダーの要素、リアルエステイトビルダーの要素も持ち合わせているからこそだと言えるでしょう。
また、新築中心だった従来の事業構造から脱却するためには、地域に発信するだけでなく、社内に対し「『多様化するニーズに対応すること』『高い社会的意義があること』『業績を安定させること』の“なぜリノベーション事業に注力するのか”という3つの目的を共有した」ことによって「こうした共通認識がベースにあるから様々な問題や課題が発生した際にも迷いなく推進することができる」と強矢社長が述べていたことが印象深いです。
単に新築市場の縮小だけではない、目的を共有した上で、事業計画、ターゲット選定、強みの確認、標準仕様の整備、販促ツール作成、リノベ専門サイトの開設、業務フローの明確化、モデルハウスの開設、継続的な販促企画および発信、常に企画の検証、人材育成、モデルハウス売却という一連の取り組みについて解説いただきました。首都圏からの移住・Uターン高予算客も狙って移住コンテンツの充実や移住ツアーの開催など地域資源を活かしたり、時流に適応したりするしなやかさも、同社の強みの一つです。

エコフィールドの直近のリノベーション事例(筆者撮影)
第2回:増子建築工業(福島県郡山市)
実家リノベーションを主なターゲットにして、明確に打ち出していることが増子建築工業の大きな特徴です。
性能向上は当然押さえた上で、実家リノベーションならではのなつかしさや思い出といった情緒的な価値をWEBコンテンツや動画で展開。その考え方は提案段階の暮らしへの寄り添いや丁寧な解体、施工に至るまで貫かれています。
「情緒的価値なんて」という声が聞こえてきそうですが、経営者の価値観に基づき「機能的価値(数字で測れる)+情緒的価値(比較されにくい)」を、内向きのエネルギーでなく、外向きに発信し提供することで、地域において大手のハウスメーカーとは一線を画すリノベ工務店としての認識につながっていると言えます。
軌道に乗るまでは時間を要しましたが、今日では新築で培った大工力、地域での信頼がリノベーション事業と乖離することなく融合したからこそ成立している点も付け加えておきます。
「これからも50数年の歴史を活かし、リノベーション事業で新たな時代に適応していきたい」と増子社長はおっしゃいます。近年は施工スタッフ中心に、新築のみならずリノベーションにおいても標準施工手引書の整備に着手しています。決してマーケティング先行になることなく、施工基準を定めて施工手順の均一化、自社が目指す施工品質の維持を図ります。
第3回目:U建築(長野県飯田市)
地元・飯田市を中心に「エアコン1台で冷暖房できる家」という住まいづくりのイメージが浸透している工務店です。従来から、表層リフォーム案件の実績はありましたが、自社が重視する性能向上リノベーションの反響や接客する体制に課題感がありました。「リノベーションモデルハウス1号棟開設の際はリノベーション事業の全体戦略が欠如していた」と、推進役である小沢常務は当時を振り返ります。
私は1号棟売却後にサポートの機会をいただき、その後はU建築が持つ強みを最大限に活かしながら仕組みを構築し、3000万円級リノベや5000万円級リノベを連続受注、想定したフルリノベ案件が続々と創出できています。2024年3月に完成したモデルハウスの2号棟は4号特例の縮小を想定した建物になっており、法改正も見据えた取り組みです。
新築をベースにリノベーション原価の整備を着々と進めており、実績を重ねるごとに精度が高まりつつあります。WEB関連は課題ですが今後優先度を上げて注力していきます。飯田市の行政人口は約10万人と限られますが、今回受講された工務店の半数近くが人口10万人未満ということもあり、小商圏ならではの事業展開も関心が高かったようです。
3社はなぜリノベを確立できたのか?
講座にご登場いただいた3社は、商圏人口や強み、差別化要素には相違点があるものの、下記のような共通点があります。
・リノベーション事業を軌道に乗せるための推進役(社長や経営幹部)の存在
・事業化に向けて部分最適ではなく、ターゲット調整、集客強化、店舗開設、仕様決め、営業フローの確立、施工体制の整備等全体構築した
・リノベーションの事業年商が3億、またはそれ以下ということもあり、新築とリノベーションで組織を分けていない(4~5億、あるいはそれ以上の事例はほぼ例外なく事業部制となっている)
・新築の強みを活かすことを重視し、新築とリノベーション事業がうまく融合できている
・いずれも事業承継タイミングという会社の転換点でリノベーション事業が重要な役割を担っている
受講された方の声も、一部ですが紹介しましょう。
・「工務店らしいリノベーションの進め方について、大変学びの多い講座だった」
・「自社の強みを発信する大切さを再認識した」
・「リノベーションのビジネスモデルを体系的に学んだ。新築事業と一貫性を持たせながらどう展開するかもヒントになった」
・「リノベーションのカテゴリー分けが明確になり、自社の進むべき方向性が定まった」
・「持ち家、中古、買取再販等パターン別の事例を聞き、自社の目指す領域が明確になった」
・「既にリノベーション事業に取り組んでいるが全体を俯瞰して現状把握する大切さに気づかされた」
以上、今回登壇された3社は、工務店らしいリノベーション事業という観点で登壇いただきました。
しかし、決してこの3社だけの特別な話ではなく、大きな領域でマイナーな存在になるより、競争が限られる領域で強みを活かすといった戦略の論理や一連の取り組みはあらゆる地域工務店に通じる普遍性があると考えています。私も、引き続き各地でキラリと光るリノベ工務店が増えるようサポートしていきます。
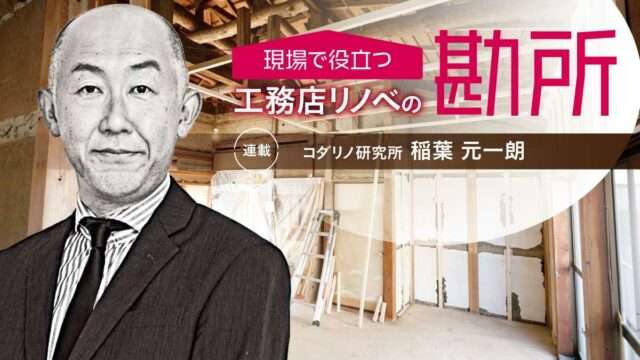
過去の連載記事一覧はこちら
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。