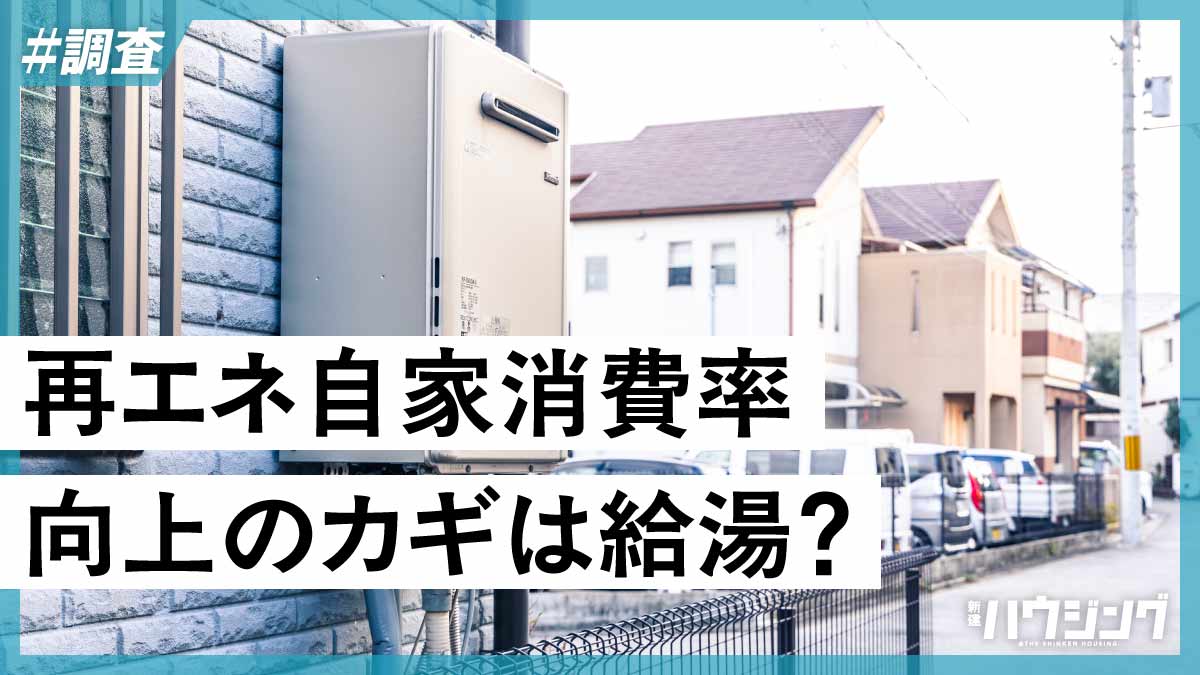新築住宅市場が縮小するなかでも、地域工務店や大工はまだまだ進化していけるポテンシャルを秘めている。
この連載では、圧倒的な世界観の住宅・建築によってInstagramのフォロワー26万人を誇り、“進化系工務店”の1タイプとして、業界内外から熱い視線を集める菱田工務店(長野県坂城町)にフォーカス。
同社代表で、大工アーティストとして国内外で活動し、「Forbes JAPAN カルチャープレナー30 2024」にも選出された菱田昌平氏が、地域工務店が手しごとをベースに進化を実現する方法論として「HISHIDAメソッド」(思想と経営手法)を解説する。
 |
菱田昌平 ひしだ・しょうへい 🔗菱田工務店 🔗大工アーティスト Shohei Hishida |
1979年生まれ、長野県坂城町出身。小学校卒業後、中学に3カ月通い、不登校に。リンゴ農家、サッシ業者などを経て大工修行へ。26歳で独立し、2012年に菱田工務店を設立。会社経営のかたわら、大工アーティスト・Shohei Hishidaとして活動。会社とは別のShohei Hishida個人のInstagramも海外の人を含めてフォロワー24万人を誇る。菱田工務店は、新築受注年間約30棟で、社員約50人。15人の社員大工を擁するものづくり集団で、墨付け・手刻みといった技術も織り交ぜた家づくりを展開。海外も含めて全国から、設計志望の若者が同社で働きたいと門を叩く。 |
episode 3
大工工務店の経営とブランディング
究めたいものづくりに集中するがゆえに、数字の管理や経営がおろそかになっていく―。
かつては自分も、小さな大工工務店の経営者が陥りがちな“沼”にハマっていた。手しごとをベースに確かなブランドを構築し、その価値に見合う適正な粗利と価格を自信を持って定め、経営的にも強い基盤をつくっていくことが必要不可欠だ。
本連載の第1回で解説したような、ものづくりを究める手しごとにこだわった家づくりを貫きながら、第2回で紹介したように継続的に意欲ある若手(設計者・大工など)を採用・育成し、次回(第4回)で語りたい未来への投資(新たなチャレンジ)を続けていく経営ビジョンを実現するために、粗利率や営業利益、販管費率など従来の業界の常識や相場にとらわれない独自の考え方で数字を設定している。
1/6 page
業界水準にとらわれない
よく業界内で、粗利の目安として25~30%という数字を聞くが、菱田工務店では、「手しごとの価値」をベースに健全経営を行うための数字から逆算して決める。
結果的に業界の一般的な水準よりも高く設定しているが、経営を安定化するためだけではなく、当社が提供している手しごとには、それだけの価値があると考えている。
 |
 |
| 「手しごとの価値」をベースにして健全経営を行うために必要な数字から逆算して粗利や価格を決定する | |
当社の家づくりには欠かすことができない数多くの設計者と大工を中心に、人件費が大きなウエートを占める。特に大工は、クラフトマンシップの源泉となっている大切な存在とはいえ、見習い期間の2~3年は確実に赤字だ。
それらも踏まえて、粗利と価格を決める。その価値に見合った価格であれば、問題なく顧客の納得感と高い満足度を得ることもできるはずだ。
工務店が主体的に粗利・価格を決定できないのは、周辺(競合など)の相場をある程度、意識せざるを得ないから。その理由としては、やはり・・・
この記事は新建ハウジング5月10日号6面(2025年5月10日発行)に掲載しています。
※この記事は会員限定記事です。ログイン後、続きが読めます。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。